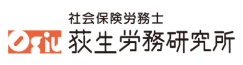「解雇予告手当」とは?支払いが必要な場面を整理
解雇予告手当とは?支払いが必要な場面と実務対応をわかりやすく整理
突然の解雇は、労働者にとって生活への影響が大きく、企業にとってもトラブル化しやすいテーマです。そこで法律は、解雇のタイミングや手続に一定のルールを設け、労働者が次の仕事を探す猶予を確保できるようにしています。その代表が「解雇予告」と、予告ができない場合に支払う「解雇予告手当」です。本記事では、支払いが必要な場面を中心に、例外や計算方法、実務での注意点を整理します。
解雇予告手当の定義と法的な位置づけ
解雇予告手当とは、会社が労働者を解雇する際に、原則として30日前までに解雇予告を行う義務があるところ、予告期間が足りない場合に不足日数分の賃金を支払う制度です。つまり「予告の代わりの金銭補償」で、支払いにより即日解雇が直ちに正当化されるわけではありません。解雇理由の相当性(客観的合理性・社会通念上の相当性)とは別問題で、手当を払っても不当解雇と判断される可能性は残ります。社労士の実務では、手当だけでリスクが消えない点を必ず説明し、手続と理由の両面で整えることが重要です。
支払いが必要になる典型パターン
支払いが必要なのは「解雇するが、30日前予告をしない(または足りない)」ときです。たとえば、今日付で解雇を通告して即日退職させるなら、原則として30日分の平均賃金相当が必要です。10日前に予告した場合は不足20日分を支払います。なお、退職勧奨(合意退職)は解雇ではないため、合意が成立している限り解雇予告手当の問題になりにくい一方、実態が強要に近いと「解雇」扱いになる争いもあります。社労士としては、合意書の作り方や説明記録の整備で紛争予防を図ります。
「解雇」と「退職」の違いで結論が変わる
実務で最も多い混乱は、会社側が「辞めてもらったつもり」でも、労働者側が「解雇された」と受け取って争いになるケースです。解雇予告手当は、会社の一方的な契約終了(解雇)で問題となります。自己都合退職、定年、契約期間満了(雇止め)などは原則として対象外ですが、雇止めが実質的に解雇に近い態様で行われた場合は別の法的問題(雇止め法理、権利濫用法理)が生じます。現場の会話だけで処理せず、通知書の文言、合意の有無、退職日設定の経緯を整理することが欠かせません。
例外:解雇予告が不要となる場合
例外として、①解雇予告除外認定を受けた場合(労働者の責に帰すべき事由による解雇、天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が困難など)、②日雇いで一定期間を超えない場合など、法律上の適用除外に該当する場合は、解雇予告や手当が不要となることがあります。ただし「重大な規律違反=当然に不要」ではなく、除外認定の手続や要件判断が肝心です。社労士としては、懲戒解雇を検討する局面ほど証拠・手続の瑕疵が致命傷になるため、就業規則の根拠、調査記録、弁明機会の付与などをセットで整えるよう助言します。
支給額の計算:平均賃金が基本
解雇予告手当は「平均賃金×不足日数」で計算するのが原則です。平均賃金は、原則として「解雇予告(または解雇)をした日の直前3か月に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総暦日数」で算出します。ここでの賃金に含める・含めない(賞与など)の判断や、最低保障、休業が多い場合の除外日調整など、実務上のつまずきが起こりがちです。給与体系が複雑な企業ほど計算根拠を明確化し、賃金台帳・出勤簿と整合する形で算定資料を残すことが、後日の説明責任に直結します。
支払いのタイミングと実務での進め方
手当は、不足日数分を補う趣旨のため、解雇の意思表示と同時期に支払う運用が基本となります。遅れれば遅れるほど「予告が適法に実施されていない」との争点になりやすく、企業側の不利要素を増やします。また、解雇日をいつにするかで、予告の要否や不足日数が変わります。社労士は、解雇予告→就労免除→有給消化→退職日設定などの選択肢を並べ、賃金・社会保険・引継ぎ・社内外への説明まで含めた手順設計を行います。社労士の観点では、解雇通知書や合意書、説明文書の作成・文言チェックで紛争予防を支援します。
トラブルを避けるための注意点
第一に、解雇予告手当を払っても「解雇が有効」になるわけではありません。不当解雇とされれば、地位確認や賃金請求が生じ得ます。第二に、懲戒解雇など「労働者の責に帰すべき事由」であっても、除外認定なく予告・手当が必要になる場合があります。第三に、退職勧奨や合意退職に見せかけた運用は、後から解雇と評価されるリスクがあり、証拠(面談記録、提示条件、検討時間の付与)が重要です。就業規則・雇用契約書・評価記録・指導記録が整っているほど、解雇の相当性判断でも有利に働きます。
まとめ:支払い要否の判断は「解雇の形」と「予告日数」がカギ
解雇予告手当は、解雇の30日前予告ができない(または足りない)ときに、不足日数分の平均賃金を支払う制度です。一方で、例外や除外認定の手続、計算の細部、そして何より解雇の有効性は別問題で、実務では複合的なリスク管理が必要になります。解雇を検討する場合は、まず「解雇か合意退職か」「予告日数は足りるか」「除外認定が必要か」「計算根拠は説明できるか」を点検し、就業規則や証拠資料も整えましょう。迷ったときは、社労士に早めに相談することで、法令順守と紛争予防の両立が図れます。
関連記事
-
No Image 就業規則の作成と労務顧問契約はどう違うの?企業が知っておくべき重要な違いとは -
【2026年4月】健康保険の扶養認定が「労働契約ベース」に。熊本の中小企業が今から整える3つの実務 【2026年4月】健康保険の扶養認定が「労働契約ベース」に。熊本の中小企業が今から整える3つの実務 -
「月給だから大丈夫」は危険!短時間正社員でも労働時間管理が必要な理由 「月給だから大丈夫」は危険!短時間正社員でも労働時間管理が必要な理由 -
解雇予告除外認定申請:審査で見られるポイントと“やってはいけない”NG例 解雇予告除外認定申請:審査で見られるポイントと“やってはいけない”NG例 -
No Image 「就業規則の絶対的必要記載事項」とは何か?労基法との関係を解説 -
フリーランス法違反「ハラスメント対策不足」が最多 東京労働局調査からフリーランスと発注企業が学ぶポイント フリーランス法違反「ハラスメント対策不足」が最多 東京労働局調査からフリーランスと発注企業が学ぶポイント