愛知県「カスハラ防止条例」から学ぶ、熊本の中小企業が取るべき対策とは?
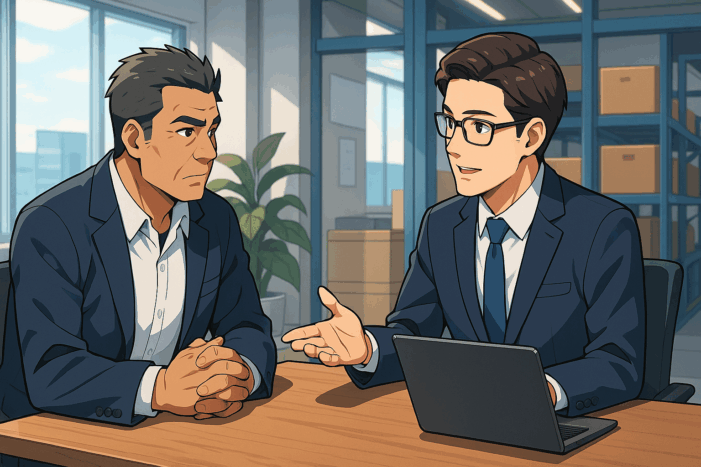
顧客対応の現場で従業員が心身に負荷を受ける「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が、全国的に社会問題となっています。愛知県では2025年10月1日、「カスハラ防止条例」が施行され、企業の取り組み強化が求められていますが、実は2026年には国レベルでの義務化も行われることをご存じでしょうか?今こそ熊本県内の企業も、先を見据えた準備が必要な時期に差しかかっています。
愛知県「カスハラ防止条例」が企業に求めるもの
条例では、カスハラを「社会通念上許容される範囲を超え、かつ就業環境を害する顧客等からの言動」と定義。以下の3点が特徴です:
1. 「何人もカスハラを行ってはならない」と明記
2. 企業に対して就業者の安全確保を「努力義務」として課す
3. 罰則はなく、実効性は企業の自主的取り組みに委ねられている
県はマニュアルや相談窓口を整備し、必要に応じて社労士等の専門家を派遣する「伴走型支援」も始めています。
2026年の「カスハラ対応義務化」が決定済み
既に国会でもカスハラ防止を目的とした法改正が実施済みで、2026年10月にも全国的な義務化が視野に入っています。
この新法により、企業は以下のような対応が法的に求められる可能性があります:
– カスハラ防止マニュアルの整備
– 教育研修の実施
– 相談窓口の設置
– 相談・記録の保存義務
罰則の有無や詳細は今後の政省令に委ねられる見通しですが、「まだ先の話」と油断することなく、今から体制整備を進める企業こそ、トラブル回避と採用力の強化につながるといえます。
当事務所が提案する3つの初動対策
1. 現場の実態把握
従業員アンケートや面談で「不当な顧客対応」の実例を把握。
2. 社内マニュアルの整備
愛知県のマニュアルをベースに、自社に合わせたルールを作成。
3. 相談体制の構築
内部相談窓口と外部専門家(顧問社労士等)を組み合わせ、継続的な対応体制を。
まとめ
「お客様は神様」という価値観に縛られていた時代から、「従業員の尊厳と安心を守る」時代へ。
今後は、企業の姿勢そのものが求職者や取引先からも問われるようになります。
国の法制化を「待つ」のではなく、「備える」ことで企業リスクを減らし、従業員からも選ばれる企業へ。
熊本県内の中小企業こそ、この転換期を前向きにとらえ、先手を打つべきタイミングです。
マニュアル整備、研修設計、相談体制の構築など、実践的な支援をご希望の方は、荻生労務研究所までお気軽にご相談ください。
関連記事
-
熊本大学×日本商工会議所青年部の人材育成協定に注目:地域経営者にとっての意味とは? 熊本大学×日本商工会議所青年部の人材育成協定に注目:地域経営者にとっての意味とは? -
熊本が国の「スタートアップ拠点都市」に選定 ─ 地元中小企業に広がる連携と成長のチャンス 熊本が国の「スタートアップ拠点都市」に選定 ─ 地元中小企業に広がる連携と成長のチャンス -
「荷待ち」「荷役」が減らない…熊本の運送会社が直面する“見えにくい負担”とは?【第2回】 「荷待ち」「荷役」が減らない…熊本の運送会社が直面する“見えにくい負担”とは?【第2回】 -
従業員エンゲージメントを高める「5つの向上要素」とは?〜経営者が実践すべき現場視点の打ち手〜 従業員エンゲージメントを高める「5つの向上要素」とは?〜経営者が実践すべき現場視点の打ち手〜 -
No Image 介護離職年10万人の現実 中小企業こそ求められる「両立支援」体制の整備とは? -
地方の中小企業にもテレワークが必要な理由 テレワークと男性育休取得促進セミナーの相談員社労士が解説 地方の中小企業にもテレワークが必要な理由 テレワークと男性育休取得促進セミナーの相談員社労士が解説
