若手が辞めない建設会社のつくり方 「平均年齢31歳」を実現した企業に学ぶ「定着戦略」
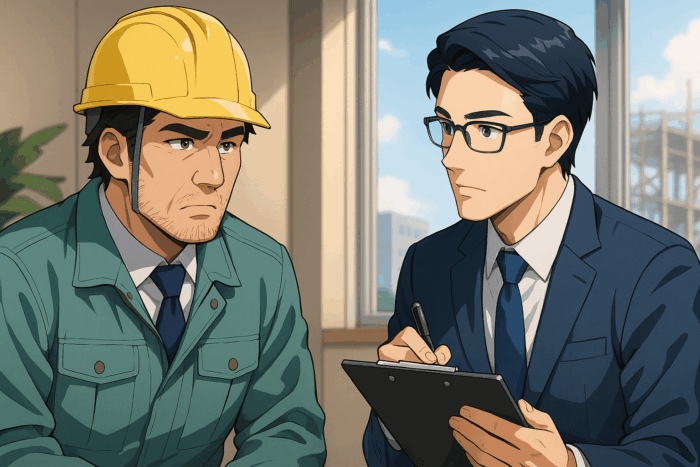
「採用しても若手がすぐ辞める…」
これは多くの建設業経営者が抱える切実な悩みです。実際、建設業の高卒新規就職者の3年以内離職率は43.2%と、全産業平均(36.9%)を大きく上回ります。
しかし、そうした業界の常識を覆し、「平均年齢31歳」「売上13倍」という成長を遂げている企業があります。本記事では、その成功事例から見える「人が辞めない建設会社づくり」のヒントを、社会保険労務士の視点でひも解きます。
建設業界の若手離職率はなぜ高いのか?
国交省や厚労省の調査によれば、建設業界は高齢化が進み、29歳以下の割合はわずか11.7%。
その原因の一つは、「身体的にきつい」「年齢の近い先輩がいない」「キャリアの見通しが持てない」といった就労環境にあると考えられます。
つまり、単に「待遇」を良くするだけでは、若手の定着にはつながらないのです。
若手が定着する企業が取り組む「3つの仕掛け」
成友興業の事例から見えてくるのは、以下のような実践的な施策です。
(1)現場負担の軽減と週休2日制を実現
ICT導入や「工事管理部」による社内業務支援で、現場の仕事量を削減し週休2日制を導入。
結果として、若手の「働きやすさ」が飛躍的に向上。
(2)労働時間を見える化し、残業管理を徹底
残業警告メール・面談による改善サイクルにより、月残業平均26.5時間・長時間労働ゼロを達成。
(3)育成制度の「見える化」と関係性の強化
メンター・エルダー制度、定期面談、キャリア設計支援を通じて、孤立感や不安を軽減。
社内全体で若手を支える「関係資本」の構築が定着の鍵。
熊本の中小建設業が取り入れるべき3つの視点
社会保険労務士として、熊本県内の企業様にも実践していただきたいのは以下の3点です。
1. 仕組みと組織化で「現場依存」から脱却する
一人の頑張りに依存せず、チームとして回せる仕組みを整えること。
2. 「気にかける文化」を醸成する
若手は“制度”以上に“関係性”で離職を判断します。日々の声掛けが最大の予防策。
3. 経営者・上司が率先して学ぶ・育てる姿勢を見せる
代表自らの面談や資格取得が、若手のロイヤルティを高めています。
まとめ
「若手が続かない」のは「時代のせい」ではありません。
制度・仕組み・文化を変えることで、建設業でも若手が活躍し定着する組織はつくれます。
当研究所では、こうした仕組みづくりの支援や、面談体制の構築、定着率改善施策の設計も承っています。
熊本県内の建設業経営者の皆様、まずは自社の「定着の壁」を見える化してみませんか?
ご相談はお気軽にどうぞ。
お問い合わせフォームはこちら
関連記事
-
No Image 年次有給休暇管理簿とは?企業が守るべき労務管理の新常識 -
個人事業主も社会保険に加入できる時代へ 今こそ“任意適用”の選択を考える 個人事業主も社会保険に加入できる時代へ 今こそ“任意適用”の選択を考える -
No Image 勤怠データ改ざんが発覚し、熊本市で企業イメージを大きく損ねた実例 -
【2026年4月】健康保険の扶養認定が「労働契約ベース」に。熊本の中小企業が今から整える3つの実務 【2026年4月】健康保険の扶養認定が「労働契約ベース」に。熊本の中小企業が今から整える3つの実務 -
助成金申請は「労務監査」から始めましょう – 荻生労務研究所の対応方針 助成金申請は「労務監査」から始めましょう – 荻生労務研究所の対応方針 -
熊本県で増える「人手不足倒産」を防ぐ! 地域企業向け・採用と定着の見える化支援とは? 熊本県で増える「人手不足倒産」を防ぐ! 地域企業向け・採用と定着の見える化支援とは?
