地域インフラに潜む「人材不足」の影響 肥薩おれんじ鉄道の減便に見る、地方企業の課題とは
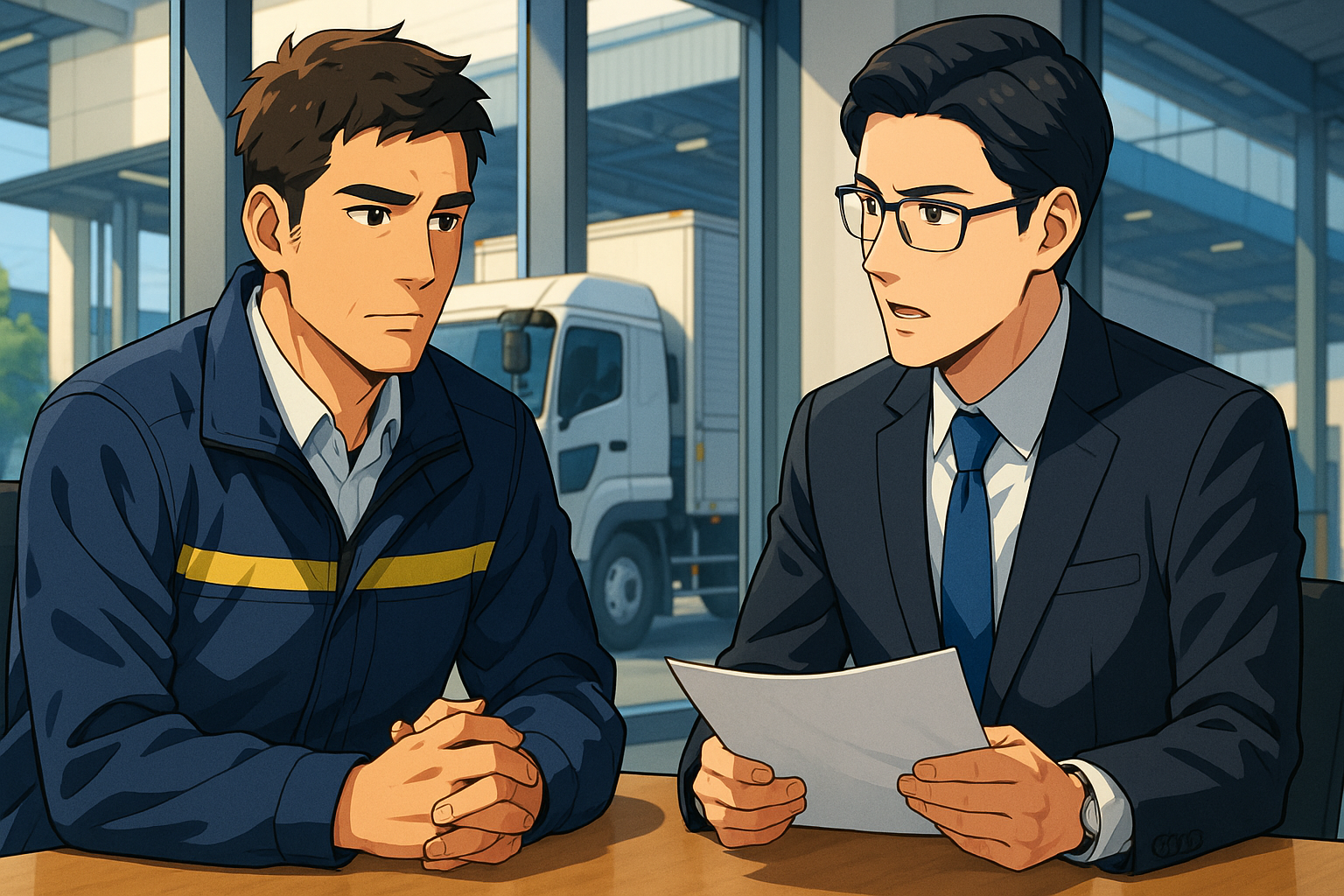
熊本と鹿児島を結ぶ「肥薩おれんじ鉄道」が、運転士不足により8月からさらに約3割の減便を発表しました。地域交通における人材不足は、中小企業経営にも少なからぬ影響を及ぼします。今回は、単なる交通の話にとどまらず、地方における人材確保・組織マネジメントの課題として考察します。
肥薩おれんじ鉄道、8月からさらに減便へ
2024年2月に上下5本の列車を運休した肥薩おれんじ鉄道が、8月からさらに3割程度の減便を行うと発表しました。定年退職などにより運転士のさらなる離職が見込まれ、現行のダイヤでは維持困難とのこと。平日は51本のうち18本、休日は46本のうち15本が運休対象となります。
利用者への影響が比較的少ない便を選定したとしていますが、代行バスや振替輸送は実施されない方針です。これは、沿線の高齢者や通勤・通学者にとっては決して小さな問題ではありません。
経営視点で捉える「人材不足」の根深さ
注目すべきは、原因が「慢性的な運転士不足」である点です。鉄道業界特有の要件(資格・シフト・責任の重さ)もありますが、この問題は地方の多くの中小企業にも通じる構造的課題です。
- 熟練人材の高齢化と退職
- 若年層の地元就職回避
- 採用しても定着しない環境や体制
このような背景のもと、運転士確保を「喫緊の課題」と語った新社長・中村氏の発言は、多くの中小企業経営者にとっても他人事ではないはずです。
今こそ求められる「経営の人事戦略」
今回のニュースから私たちが学ぶべきは、業種に関わらず「人材の持続可能性」を経営の中心に置く必要性です。具体的には:
- 採用よりも「定着と育成」を重視する方針転換
- 柔軟な働き方や兼業・副業の受け入れ
- 業務の見直しによる負担軽減と効率化
- ローカルに根ざした魅力発信(地域密着採用)
特に熊本県内の中小企業にとっては、「人がいない」ことよりも「人が定着しない」ことがボトルネックになりがちです。外部環境に起因する問題に対して、自社が主体的にできることを見直す好機でもあります。
まとめ
鉄道会社のニュースに見えるのは、地域経済と生活インフラを支える人材不足の現実です。これは、そのまま中小企業経営に跳ね返ってくるテーマでもあります。
人を「コスト」ではなく「未来を支える資源」と捉える視点を持てるかどうか——。その姿勢が、これからの地方企業の持続性を大きく左右すると感じています。
貴社では「人材の見直し」にどのように取り組んでおられますか?
関連記事
-
社会保険は経営の土台:大学発スタートアップに必要な基礎知識 社会保険は経営の土台:大学発スタートアップに必要な基礎知識 -
賃金のデジタル払い、ついに本格運用へ?熊本県内中小企業が知っておきたいポイント 賃金のデジタル払い、ついに本格運用へ?熊本県内中小企業が知っておきたいポイント -
【2026年最新】中小企業経営者が知るべき「社会保険料削減スキーム」の危険性と正しい対策 【2026年最新】中小企業経営者が知るべき「社会保険料削減スキーム」の危険性と正しい対策 -
学生アルバイトが活躍する大学発ベンチャー、自由出勤制はアリ?労務管理と雇用契約の落とし穴 学生アルバイトが活躍する大学発ベンチャー、自由出勤制はアリ?労務管理と雇用契約の落とし穴 -
最低賃金が過去最大の平均63円引き上げへ──熊本の中小企業が今すべきこととは?【2025年最新】 最低賃金が過去最大の平均63円引き上げへ──熊本の中小企業が今すべきこととは?【2025年最新】 -
【テレビ出演のお知らせ】熊本朝日放送「くまもとLive Touch」にてカスタマーハラスメント対策についてコメントしました 【テレビ出演のお知らせ】熊本朝日放送「くまもとLive Touch」にてカスタマーハラスメント対策についてコメントしました
