「イクメン」から「共育」へ──男性育休のこれからと中小企業に求められる対応とは?
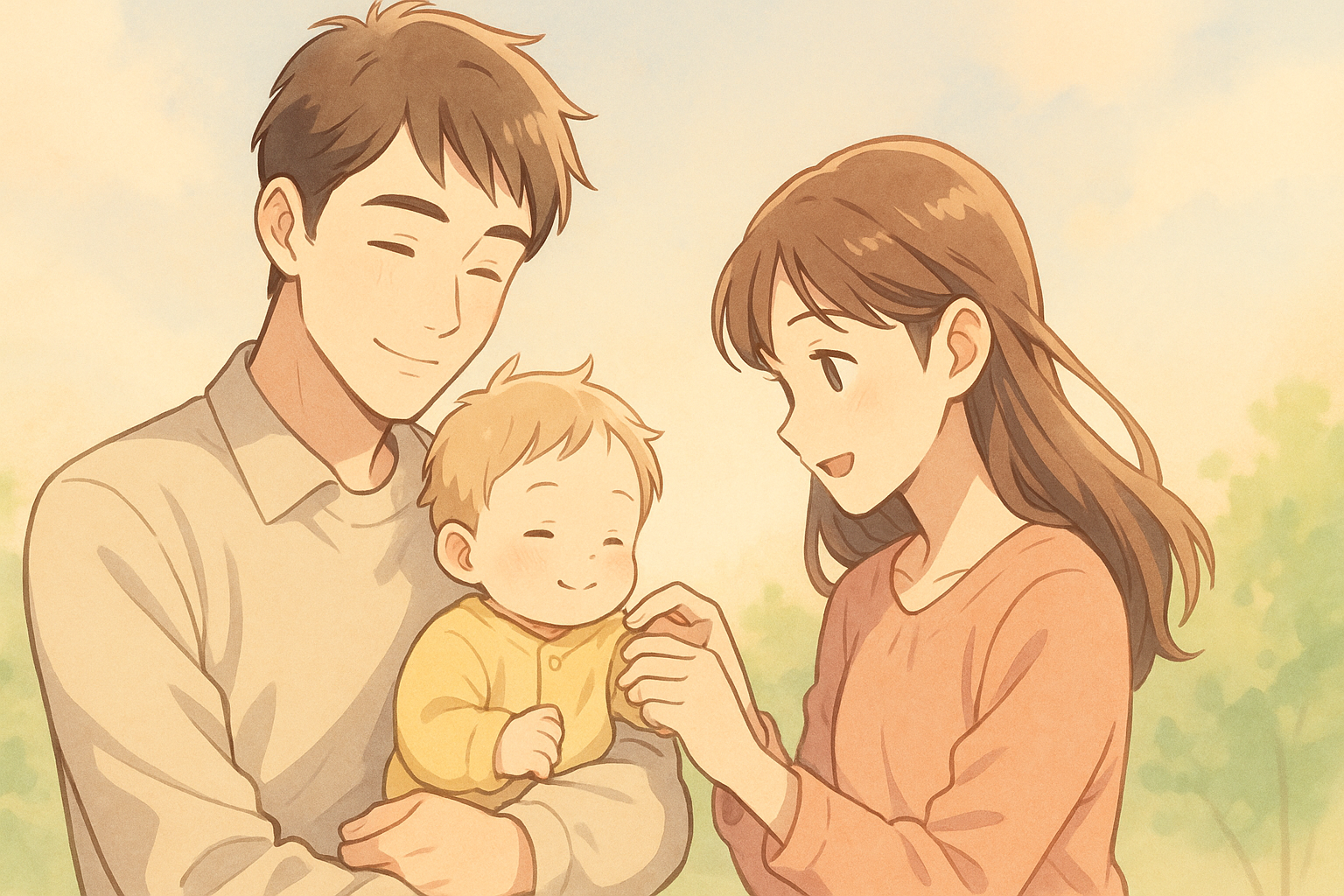
「男性育休」の在り方が、今、大きく見直されています。厚生労働省は長年続けてきた「イクメンプロジェクト」を終了し、2025年からは「共育プロジェクト」が始動。時代に即した名称変更の背景には、育休の“質”に目を向ける必要性があります。中小企業経営者として、今何を理解し、どう対応すべきか。社会保険労務士の立場から考察します。
「イクメン」プロジェクトの終焉と「共育」への移行
2009年に始まった「イクメンプロジェクト」は、男性の育児参加を社会的に後押ししてきました。当時1%台だった男性の育休取得率は、2023年度には30.1%まで上昇。一定の成果を収めた一方で、「取るだけ育休」にとどまり、実際の育児負担の偏りは是正されていない現実があります。
こうした課題を踏まえ、2025年度からは新たに「共育(ともいく)プロジェクト」が始動。単なる取得率の向上だけでなく、「職場の風土改革」「育児参画の実質化」が重視されます。
中小企業に求められる視点:取得支援から風土づくりへ
男性育休の促進は、大企業だけの話ではありません。むしろ職場の人員体制が限られる中小企業こそ、制度運用や職場の理解づくりが成否を分けます。重要なのは以下の3点です:
1. 制度の明文化と社内周知
育休制度の存在を周知し、男女ともに安心して取得できる職場ルールを整える。
2. 業務の平準化・引継ぎ体制の整備
育休取得者の不在を補えるように、日頃からの業務の見える化と共有が必要です。
3. 管理職への研修と意識改革
取得者本人以上に、上司や周囲の理解が取得と活用の鍵となります。
「共育」の時代、中小企業が果たすべき社会的役割
「共育」は、単に男性の育休取得を奨励するだけでなく、家庭内・職場内の“無意識の偏り”を問い直すものでもあります。たとえば、「育休は女性のもの」「子どもの病院は母親が行くべき」といった固定観念は、職場でも見られがちです。
こうした意識を変えることは、企業の働きやすさ・魅力づくりに直結します。人手不足が深刻化する中、男女問わず安心して働き続けられる職場づくりは、経営課題そのものです。
まとめ
「育休を取らせること」から「育児参画を支える職場文化」へ──「共育」への転換は、私たち中小企業経営者にとっても他人事ではありません。今こそ制度と風土の両面から見直し、実効性ある取り組みを進めていきましょう。
関連記事
-
スタッフがサングラス? 熊本城の「暑さ対策」から考える、企業に求められる熱中症対策の現在地 スタッフがサングラス? 熊本城の「暑さ対策」から考える、企業に求められる熱中症対策の現在地 -
テレワークは定着したのか? 都市圏調査から見える「これから」の働き方 テレワークは定着したのか? 都市圏調査から見える「これから」の働き方 -
最低賃金の引き上げ、企業経営への影響は?─政治化の背景と中小企業が取るべき対応策 最低賃金の引き上げ、企業経営への影響は?─政治化の背景と中小企業が取るべき対応策 -
熊本市電「非正規79人」問題にみる、地域公共インフラと雇用の課題 熊本市電「非正規79人」問題にみる、地域公共インフラと雇用の課題 -
生成AIの導入で生産性向上 今すぐ取り入れたい3つの活用法 生成AIの導入で生産性向上 今すぐ取り入れたい3つの活用法 -
【内部不正2.4億円】ガンホー事件に学ぶ「架空発注」防止策と中小企業が今すぐできること 【内部不正2.4億円】ガンホー事件に学ぶ「架空発注」防止策と中小企業が今すぐできること
