「良かれと思って」が命取りに?発達障害社員の情報共有で起きた労務トラブル
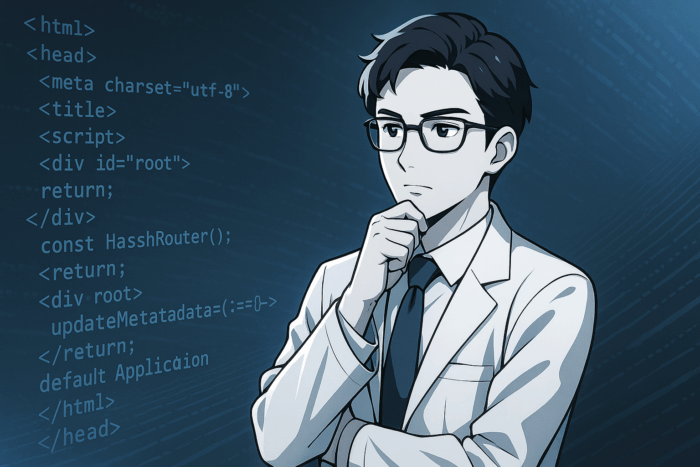
配慮のつもりがトラブルの火種に
近年、精神疾患や発達障害を抱える従業員の雇用に関するご相談が増えています。その中で、あるケースをご紹介します。中小企業で新たに採用した社員が、自身に発達障害があることを入社時に自己申告し、一定の配慮を希望しました。企業側としても誠意を持って対応しようとし、配属先の同僚たちに「この社員は発達障害があるため、配慮をお願いします」と伝達しました。
しかし後日、この社員との間に信頼関係の崩壊が起こり、結果として労務トラブルに発展してしまったのです。
精神・発達障害者の雇用でなぜ問題が起きやすいのか?
精神疾患や発達障害を持つ方々の雇用は、企業の多様性推進にとって重要な一歩です。しかし、配慮すべきポイントを見誤ると、トラブルにつながるリスクが高まります。特に注意すべきなのが「病歴や障害名などの個人情報」の取り扱いです。
こうした情報は、個人情報保護法上「要配慮個人情報」に分類され、企業がどのように取り扱うかについて厳格なルールが定められています。
こんな対応、実はNGだった?
先ほどのようなケースでは、本人の同意を得ずに、同僚に対して発達障害に関する情報を伝達したことが問題となります。
たとえ社長や上司が「配慮のために必要」と判断したとしても、本人の明確な同意なしに病歴を第三者に伝えることは法的にNGです。
厚生労働省も、障害者の雇用管理に関して、個人情報の適切な管理を強く求めています。違反すれば、企業の信頼を失うばかりか、法的な責任を問われる可能性もあります。
トラブルを防ぐために今すぐできること
精神障害や発達障害を抱える社員の雇用では、以下の対応が極めて重要です:
- 本人の同意を得ない限り、障害名や病歴を他者に伝えない
- 障害への配慮が必要な場合は、どのような配慮が業務上必要かを本人と丁寧にすり合わせる
- 「誰が」「どの情報を」「どのように取り扱うか」について、社内ルールを明文化する(健康情報取扱規程の策定)
- 管理職・現場リーダーにも教育を徹底する
これらを実施することで、配慮と法令遵守を両立し、企業としての信頼性も高められます。
「うちも同じかも」と思ったら
「うちの対応、大丈夫だろうか?」と不安を感じた方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
当事務所では、精神疾患・発達障害を持つ社員の雇用に関する初回無料の労務相談を実施しております。
問題が大きくなる前に、気軽にご相談いただくことで、リスクを最小限に抑えることができます。経営者の皆さまが安心して雇用に取り組める環境づくりを、全力でサポートいたします。
関連記事
-
改正旅費法対応と就業規則変更の実務ポイント|熊本県内企業向け 改正旅費法対応と就業規則変更の実務ポイント|熊本県内企業向け -
保護者を巻き込んだ企業見学ツアーの可能性とは? 〜長崎県・熊本県の取り組みから読み解く、採用広報の新たな視点〜 保護者を巻き込んだ企業見学ツアーの可能性とは? 〜長崎県・熊本県の取り組みから読み解く、採用広報の新たな視点〜 -
若手人材の定着に効く「奨学金返還支援制度」栃木県と熊本県の事例から考える中小企業の実務対応 若手人材の定着に効く「奨学金返還支援制度」栃木県と熊本県の事例から考える中小企業の実務対応 -
最低賃金引上げ直前対策|業務改善助成金で「賃上げできる会社」に 最低賃金引上げ直前対策|業務改善助成金で「賃上げできる会社」に -
猛暑下の職場環境改善に必要な視点とは? 熊本市給食調理場エアコン設置報道から考える法的義務と企業の対応 猛暑下の職場環境改善に必要な視点とは? 熊本市給食調理場エアコン設置報道から考える法的義務と企業の対応 -
社労士は、もっと知られてもいい。-専門8士業合同無料相談会に参加して- 社労士は、もっと知られてもいい。-専門8士業合同無料相談会に参加して-
