部下の「行動」ではなく、「結果」に焦点を当てる指導法
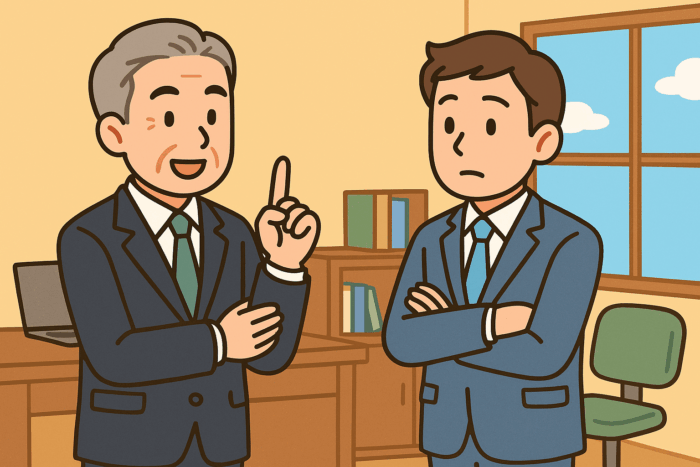
先日、カスタマーハラスメントに関するセミナーを実施した際に、参加者からこんな質問をいただきました。
「顧客対応に問題がある社員に対して、反発を招かずにどう指導すれば良いか」。
現場でマネジメントを担う立場の方にとって、非常にリアルで切実な問いだと思います。
特に接客や顧客対応のような“態度”や“言い方”に関する指導は、どう伝えるかに気を使う場面が多くあります。
部下の「行動」を責めるのではなく、「結果」に焦点を当てる
このご質問を受けて、私がお話ししたのは「部下の行動そのものを責めない」ということでした。
たとえば、「その応対の仕方はよくないから、やめなさい」といった伝え方をしてしまうと、「自分のやり方を否定された」と受け取られてしまう可能性があります。
これは、指導のつもりがかえって反発を生みやすくなるケースです。
部下の行動に直接ダメ出しをするのではなく、「その行動が結果的にどういう影響を及ぼすのか」という“結果”に焦点を当てる。
そして、「こういう結果を防ぐためには、別のやり方があるのではないか」と提案する形にすることで、受け手の受け止め方が大きく変わってきます。
「結果に焦点を当てる」指導の具体例
例えば、部下の接客がぶっきらぼうで、お客様にあまり寄り添えていないような応対だったとします。
このとき、「その態度ではトラブルになる」と直接伝えるよりも、
「今のような応対が続くと、お客様に誤解を与えたり、必要以上に不満が大きくなってしまう可能性がある。
そうなると、余計なエスカレーションや対応が発生して、結果的に自分たちの負担も増えてしまう。
それを防ぐために、こんなふうに話してみるのはどうだろう?」
といった伝え方の方が、相手にとっても受け入れやすくなります。
このように、“行動”ではなく“結果”に視点を置いて伝えることによって、指導の場が「責められている」空気ではなく、「一緒に良くしていこう」という建設的な場に変わります。
これは、日々のマネジメントでも非常に役立つ考え方だと思います。
特に、最近は価値観の多様化もあり、「正しい伝え方」に悩む管理職の方も増えています。
その中で、「なぜそれが問題なのか」を“結果”から逆算して説明する方法は、部下の納得感を得ながら行動改善を促す一つの有効なアプローチだと感じています。
もし似たような場面があれば、ぜひ試してみてください。
関連記事
-
寄稿「男性育休で人手不足を解決する方法」が、「KUMAMOTO地方経済情報」10月号に掲載されます。 寄稿「男性育休で人手不足を解決する方法」が、「KUMAMOTO地方経済情報」10月号に掲載されます。 -
賞与で逃げても意味がない? 傷病手当金・年金が減る“危険な報酬設計” 賞与で逃げても意味がない? 傷病手当金・年金が減る“危険な報酬設計” -
熊本県が中小企業のDXを全面支援へ 「協力企業の紹介」と「人材育成」で実務を後押し 熊本県が中小企業のDXを全面支援へ 「協力企業の紹介」と「人材育成」で実務を後押し -
高齢者の賃金制度はどう変わる?熊本での最新動向と対策 高齢者の賃金制度はどう変わる?熊本での最新動向と対策 -
求人が集まらない理由と解決策:応募者が注目するポイントを徹底解説 求人が集まらない理由と解決策:応募者が注目するポイントを徹底解説 -
TSMC熊本第2工場の建設延期報道──地元中小企業への影響と対応策 TSMC熊本第2工場の建設延期報道──地元中小企業への影響と対応策
