熊本の中小企業が知っておくべき生成AIの3大リスクとは?
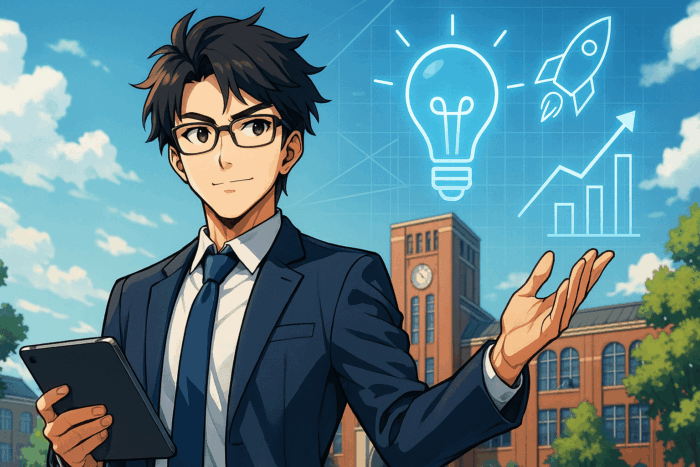
近年、業務の効率化を目的に生成AIを導入する企業が増えています。熊本県内でも、特に中小企業の現場でその活用が進んできました。しかし、その裏には見逃せないリスクも存在しています。
この記事では、私自身が熊本で社会保険労務士として中小企業の皆さまと接する中で感じている、現場で実際に起こりうる「生成AI活用における3つのリスク」と、その具体的な事例と対策をお伝えします。
1.情報漏洩:小さな油断が信用を失う原因に
例えば、人事情報や給与情報などを生成AIに入力した結果、情報が保存されてしまい、思わぬ形で外部に漏れてしまう危険性があります。
熊本のある企業では、採用面接で得た個人情報を無意識にAIに入力してしまい、その後、誤って他の用途で出力されたという事例もあります。
熊本の企業に必要な対策:
- 社内でのAI利用ルールの明文化
- 情報の匿名化・データ管理体制の見直し
2.誤情報生成(ハルシネーション):間違った法的判断はトラブルの元
「熊本地裁の判例を参考にした就業規則を作りたい」といった意図でAIに相談したところ、存在しない判例を提示された事例もあります。
特に労務分野では、誤った情報をもとに手続きを進めると、労基署からの指摘や、従業員とのトラブルに発展しかねません。
対策:
- 出力情報の裏取りをルール化
- 熊本労働局のガイドラインや専門家の意見を必ず確認
3.著作権侵害:善意の活用がトラブルを招くことも
AIが出力した文章や画像が、実在する著作物に似てしまい、意図せず著作権を侵害してしまうケースがあります。
例えば、地元の観光資源を紹介するパンフレット作成でAIを使ったところ、他地域の自治体サイトの表現をそっくり真似てしまっていた、という話もありました。
対策:
- 出力内容のチェック体制を構築
- 熊本県弁護士会など専門機関のアドバイスを活用
熊本の中小企業の皆さまへ
生成AIの導入は、効率化だけでなく、競争力強化にもつながる可能性があります。しかし、それを活かすには「正しく使う」ための知識と体制が欠かせません。
当事務所では、熊本の企業様に向けたAI導入支援や労務リスク管理のご相談を承っております。生成AIを安心して活用できる環境を、一緒に整えていきましょう。
関連記事
-
No Image 熊本県企業におけるメンタルヘルス対策と労務顧問の連携 -
令和7年10月から変更:「19歳以上23歳未満の被扶養者」年間収入要件が150万円未満に引き上げ 令和7年10月から変更:「19歳以上23歳未満の被扶養者」年間収入要件が150万円未満に引き上げ -
テレワークで、会社を伸ばす方法 テレワーク実践と男性育休取得促進セミナー相談員を担当して テレワークで、会社を伸ばす方法 テレワーク実践と男性育休取得促進セミナー相談員を担当して -
No Image 熊本市の運送会社で「変形労働時間制」の導入ミスにより未払いが発生した話 -
介護業界の人手不足対策に一手 埼玉県「介護のみらいサポートセンター」開設に学ぶ 介護業界の人手不足対策に一手 埼玉県「介護のみらいサポートセンター」開設に学ぶ -
熊本大学に全国初の「半導体学士課程」誕生 中小企業にとってのチャンスとは 熊本大学に全国初の「半導体学士課程」誕生 中小企業にとってのチャンスとは
