中小企業にも導入可能?「選択定年制」の設計と留意点〜大東建託の事例に学ぶ〜
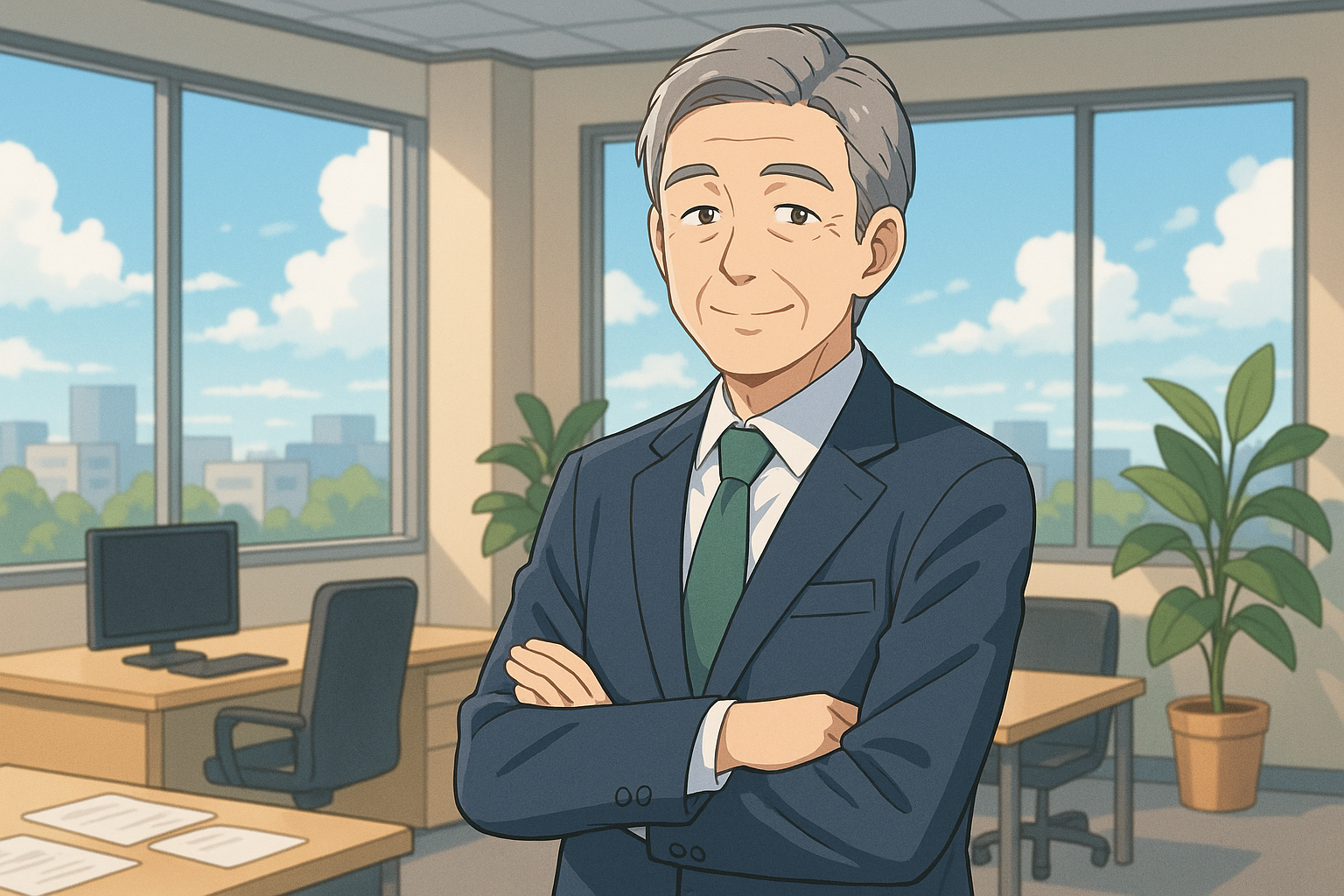
2025年4月、大東建託が導入する「選択定年制」が注目を集めています。定年を60〜65歳の間で社員が選べる制度で、再雇用後も役職や報酬の維持が可能という新しいアプローチです。高年齢者雇用が避けて通れない課題となる中、小規模企業でも応用できるヒントが詰まっています。社会保険労務士としての実務視点から、この制度の設計ポイントと中小企業での導入の可能性を整理してみましょう。
大東建託の「選択定年制」とは
同社は、社員が57歳で希望を表明し、59歳で最終決定する形で、定年年齢を60〜65歳の間から選べる制度を導入します。定年後は最長70歳(営業職は75歳)まで再雇用が可能で、選択した年齢によって退職金積立も変動するという、社員のライフプランに寄り添う仕組みです。
注目すべきは、定年後も評価次第で役職・報酬を維持できる点。これは「年齢」より「パフォーマンス」を重視する明確なメッセージでもあり、人材の活性化にもつながる制度設計です。
「役職継続基準」と人材の新陳代謝
管理職層に対しては、「直近2回の評価で基準点を満たせば役職維持、満たせなければ降格」というルールが明確に示されています。加えて、上級管理職は段階的に、下級管理職や非管理職は一括で「シニアコース」へ移行する仕組みです。
この制度は、年功的な慣習から脱却し、能力・実績を重視した組織運営へのシフトを目指すものであり、特に事業承継期にある企業にとっては参考になります。
中小企業でも導入できるか?
ポイントは以下の3点です。
1. 定年年齢の「選択制」導入は、就業規則の整備と人事制度の見直しが前提
中小企業でも、制度の簡素化と透明性を確保すれば対応可能です。
2. 評価制度の設計が肝心
公平で納得性ある評価がないと、役職維持・降格の判断が難航します。可能な限りシンプルな評価軸の導入がカギです。
3. 報酬設計と再雇用のバランス
再雇用後の報酬を現役時代の9割に抑えるなど、財務的な工夫も必要です。あくまで長期雇用の仕組みとしての視点が重要です。
おわりに
選択定年制は、「高年齢者=再雇用=補助的業務」というこれまでの常識を塗り替える可能性を秘めています。中小企業であっても、自社の人材・評価・報酬のバランスを見直すことで、より柔軟で持続可能な人事制度の構築が可能です。
今後の人材戦略の参考として、今回の事例を社内でもぜひ議論してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士 荻生労務研究所
代表 荻生清高
関連記事
-
起業家女性へのセクハラ問題|スタートアップ業界の「構造的リスク」と法整備の課題 起業家女性へのセクハラ問題|スタートアップ業界の「構造的リスク」と法整備の課題 -
熊本県の企業向け:介護離職を減らす従業員周知の具体策 熊本県の企業向け:介護離職を減らす従業員周知の具体策 -
医師の時間外労働上限規制 評価手続に関するホームページが公開 医師の時間外労働上限規制 評価手続に関するホームページが公開 -
厚生労働省が「SNS募集」の情報開示ルールを明文化 中小企業が気をつけるべき3つのポイント 厚生労働省が「SNS募集」の情報開示ルールを明文化 中小企業が気をつけるべき3つのポイント -
社会保険は経営の土台:大学発スタートアップに必要な基礎知識 社会保険は経営の土台:大学発スタートアップに必要な基礎知識 -
No Image 熊本市で起きた「解雇トラブル」が会社のSNS炎上を招いた経緯
