「デジタル化」で終わらせないために 長野の中小企業が挑んだ本当のDXとは
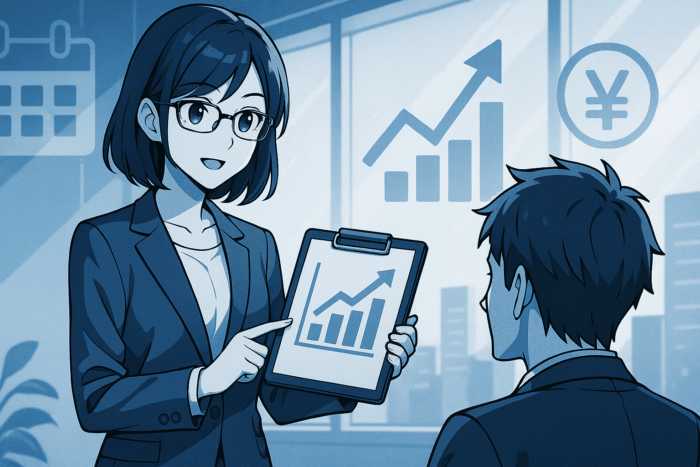
「DX」と聞くと、多くの方が「業務のデジタル化」や「効率化」を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、真のDXは単なる業務改善ではなく、ビジネスそのものの変革を意味します。今回ご紹介する長野県の中小企業・長野テクトロンの挑戦には、熊本県内の中小企業経営者にも大いに参考になる視点があります。
DXとは「変革」である
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、「アナログをデジタルに置き換えること」ではありません。デジタル技術を活用して、業務やプロセス、製品・サービス、さらには企業文化までを変革し、持続可能な競争優位性を確立することが目的です。
長野テクトロンはこの「本来の意味でのDX」に取り組んだ企業の一つです。キーボードや精算機に使われる薄型スイッチ「メンブレンスイッチ」の製造を主力とする同社は、大手からの大型受注が減少する中、「市場から取り残される」という強い危機感を持ちました。
DXの出発点は「危機感」
同社の代表取締役・柳澤由英氏は、「新たな事業を生み出すためには、まず既存業務の時間を削減する必要がある」と考えました。業務のデジタル化によって余力を生み出し、従業員が新しい取り組みに前向きに関われる環境を整える。その第一歩が、セキュリティインシデント対応でした。
サイバー攻撃という想定外の出来事が、社内整備の遅れを浮き彫りにしました。しかし、この困難をきっかけに同社は専門家の力を借りて社内体制を整え、真のDXへと踏み出します。
DXの本質は「組織文化」の変革
長野テクトロンの取り組みで注目すべきは、DXを「現場任せ」にしなかった点です。専門家の支援を得ながら、現場の声を聞き、段階的に改革を進め、従業員の理解と納得を得るプロセスを重視しました。
熊本県内でも、「とりあえずITツールを導入したけれど、現場がついてこない」というケースをよく耳にします。DXにおいて重要なのは、ツールの選定や導入以上に、「なぜ変わる必要があるのか」を全社で共有すること。そして、従業員一人ひとりが納得し、変化を前向きに捉えられる組織文化をつくることです。
熊本の中小企業が学べること
長野テクトロンの事例は、地方の中小企業にとって極めて現実的かつ示唆に富んでいます。限られた人材・資源の中でも、DXの本質を捉え、外部の専門家と連携しながら、組織全体で変革に取り組むことは可能です。
熊本の経営者の皆さん、DXを単なる業務効率化と捉えるのではなく、将来の事業存続・成長の鍵として、今一度「変革」という視点で向き合ってみませんか?
関連記事
-
退職自衛官を「即戦力」として迎える――中小企業にこそ広がる可能性 退職自衛官を「即戦力」として迎える――中小企業にこそ広がる可能性 -
熊本の労働市場に何が起きる? TSMC進出後の人手不足と賃金上昇の未来 熊本の労働市場に何が起きる? TSMC進出後の人手不足と賃金上昇の未来 -
小学館・光文社がフリーランス法違反で初の勧告|熊本の中小企業に必要な「他人事ではない」視点 小学館・光文社がフリーランス法違反で初の勧告|熊本の中小企業に必要な「他人事ではない」視点 -
「60歳の崖」を越えるために:熊本県中小企業が今から備えるべき再雇用制度の見直し 「60歳の崖」を越えるために:熊本県中小企業が今から備えるべき再雇用制度の見直し -
従業員を守るために退職勧奨を決断する―経営再建に必要な人事対応とは 従業員を守るために退職勧奨を決断する―経営再建に必要な人事対応とは -
中小企業の人材育成、今こそ「伴走型支援」の活用を 厚労省報告書が示す未来戦略 中小企業の人材育成、今こそ「伴走型支援」の活用を 厚労省報告書が示す未来戦略
