建設業の「時間外削減」に受発注者の協議が本格化。熊本県の経営者が今から備えるべき視点とは
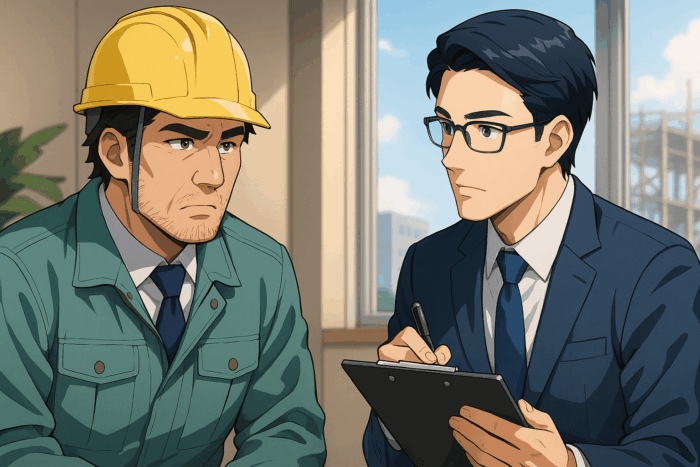
2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が全面適用され、業界内では対応の差が顕在化しつつあります。神奈川労働局が実施した受発注者協議会の取り組みは、他県の建設業経営者にとっても重要な示唆を含んでいます。熊本県内の建設業経営者が今から準備すべきポイントを、社会保険労務士としての視点で整理します。
神奈川労働局の「受発注者協議会」が示す方向性
2024年6月24日、神奈川労働局が建設業の時間外労働削減に向けた「受発注者協議会」を開催。労働局によると、同県の建設業は全産業よりも年間の総実労働時間が約100時間長い状況であり、自主的な取り組みの強化が求められています。
協議会では、発注者(元請)と受注者(下請)がともに「上限規制への対応はできているが、生産性向上には課題が残る」との認識を共有。今後は取り組みの成果を踏まえた改善サイクルが求められます。
「自主的な取組み」の裏にある、監督強化の可能性
今回の協議会では、神奈川労働局の労働基準部長が登壇し、「自主的な取組みを進めてほしい」と強調していますが、これは裏を返せば「現場での是正が進まなければ、監督指導を強化する」というメッセージとも受け取れます。
特に建設業においては、特例的に適用が遅れていた時間外労働の上限規制が2024年から全面施行され、今後の法令遵守状況は全国的にも注視されています。
熊本県内でも、労働基準監督署において、労働時間や36協定の運用状況、記録管理などの実態がより厳しくチェックされる可能性があります。経営者としては、形式的な対策ではなく「実態改善」に踏み込んだ対応が必要です。
熊本県の建設業にも「連携による改善」が求められる
神奈川での動きは、熊本県の建設業経営者にとっても他人事ではありません。今後、地方でも労働局主導の連携協議が進められる可能性があります。
現場では、元請からの納期・工程管理と、下請側の人員確保や安全管理が乖離しているケースが依然として多く見られます。このギャップを埋めるためには、「協議会」のような仕組みを自社単位、地域単位でつくることが有効です。
実務上の備え:今できる3つのアクション
1. 発注者との工程協議の場を定期化する
曖昧な納期設定や急な変更を防ぎ、業務の平準化を図ります。
2. 就業規則・36協定の見直しと実効性の確保
法定上限内に収まっていても、形式的な運用では実態改善にはつながりません。
3. ICT・省力化機器導入の検討
施工管理アプリやクラウド勤怠管理ツールなど、業務効率化の投資は生産性向上と直結します。
おわりに
建設業界の「働き方改革」は、いまや受発注構造そのものを見直すフェーズに入っています。熊本県でも、今後同様の動きが加速することが予想されます。経営者として、自社単独ではなく「つながり」で改善していく視点が、これからの競争力に直結するでしょう。
当事務所では、建設業特有の労務管理支援も多数対応しております。お気軽にご相談ください。
関連記事
-
生成AIで変わる働き方改革 熊本県の社労士が教える実践術 生成AIで変わる働き方改革 熊本県の社労士が教える実践術 -
職場の人間関係トラブルが最多に:「解雇・退職」を上回る労働相談の実態とは? 職場の人間関係トラブルが最多に:「解雇・退職」を上回る労働相談の実態とは? -
【注意喚起】2025年熊本県の最低賃金引き上げと「月給制の落とし穴」―経営者が確認すべきポイント 【注意喚起】2025年熊本県の最低賃金引き上げと「月給制の落とし穴」―経営者が確認すべきポイント -
熊本県でDE&Iを活かす職場作り|社労士が伝えるポイント 熊本県でDE&Iを活かす職場作り|社労士が伝えるポイント -
実質賃金プラス定着のカギは「中小企業の持続的賃上げ」――2025年春闘の最終集計から読み解く 実質賃金プラス定着のカギは「中小企業の持続的賃上げ」――2025年春闘の最終集計から読み解く -
No Image 「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違いを社会保険労務士が解説
