有期雇用「10年特例」成立の舞台裏から読み解く、労務リスクと制度設計の盲点
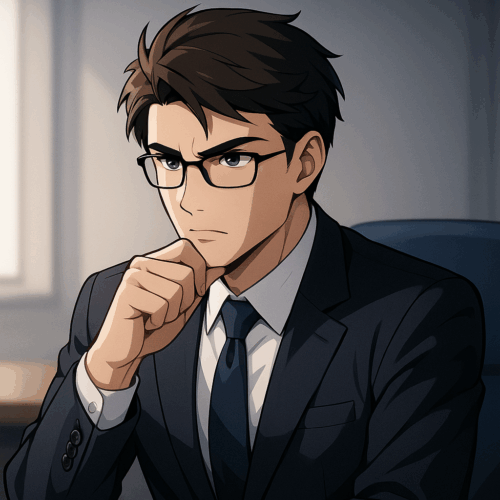
2023年春、全国の研究機関で多数の研究者が雇い止めにあいました。その背景には、2013年に導入された「10年特例」があります。制度創設時に危惧されていた「10年後の危機」が現実となった今、私たち中小企業経営者は何を学ぶべきでしょうか?
「無期転換ルール」と「10年特例」の関係
2012年に改正された労働契約法により、有期契約が5年を超えると、労働者に無期雇用へ転換する権利が発生します。このルールは本来、雇用の安定を目的としたものでした。しかし、大学・研究機関では財源の制約により、無期雇用に踏み切れず、むしろ雇い止めが増える事態を招きかねないと懸念されました。
これを受けて2013年、「研究者に限り無期転換を10年に延長できる」という特例が立法化されました。京都大学iPS細胞研究所所長(当時)山中伸弥教授らの訴えもあり、研究環境を守る目的でしたが、その実効性は限定的でした。
特例の影で先送りされた構造課題
2023年4月、「10年」の期限を迎え、多くの研究者が無期転換直前に契約終了を迎えました。特に理化学研究所での大量雇い止めは、制度の不備を象徴する出来事でした。背景には、国立大学法人の運営費交付金の削減、競争的資金への依存、人件費原資の不透明さといった構造問題がありました。
制度上は雇い止め回避が求められていたものの、実効性ある財源措置は講じられず、研究現場の雇用安定は実現しませんでした。筑波大学・柳沢教授の「競争的資金を無期雇用原資にするのは困難」との指摘も、本質を突いています。
中小企業にとっての示唆
この一連の問題は、一見すると研究機関固有の話に見えますが、実は中小企業にも大きな示唆を与えます。
第一に、法改正による労務コストの変化に対して、安易な先送り策はリスクを増幅させるということ。第二に、雇用制度は制度設計だけでなく、現場の財務体力・運用実態との整合性が問われることです。
中小企業でも、無期転換ルールや同一労働同一賃金、高年齢者雇用安定法改正など、人件費に影響する法制度が増加しています。「法令対応=規則変更」だけに留まらず、「財源や運用体制の整備」も含めた戦略的な労務設計が求められます。
まとめ
「10年特例」は、善意と現場の声に基づいた制度でしたが、「構造的課題の解決なくして制度の持続性は担保できない」という現実を突きつけました。
私たち中小企業も、自社の制度設計と運用体制を改めて点検し、変化に強い雇用戦略を構築していく必要があります。制度の持つ意味を正しく理解し、先手の対応を心がけましょう。
関連情報
関連記事
-
熊本の運送業者の皆様へ 労働時間上限規制の重要ポイント 熊本の運送業者の皆様へ 労働時間上限規制の重要ポイント -
大規模災害から会社と従業員を守るために経営者が知っておくべき備えと行動 大規模災害から会社と従業員を守るために経営者が知っておくべき備えと行動 -
No Image 最低賃金1,016円で社会保険の壁が崩れる?パートの労働時間再検討を急げ -
コールセンターにおける「カスハラ」対策認定制度の開始──中小企業にも求められる環境整備 コールセンターにおける「カスハラ」対策認定制度の開始──中小企業にも求められる環境整備 -
テレワークは定着したのか? 都市圏調査から見える「これから」の働き方 テレワークは定着したのか? 都市圏調査から見える「これから」の働き方 -
熊本の飲食業にも広がる高齢者採用:就業規則とリスク対応のポイント 熊本の飲食業にも広がる高齢者採用:就業規則とリスク対応のポイント
