令和7年度版キャリアアップ助成金の注意点 申請前に見直すべき労務管理とは
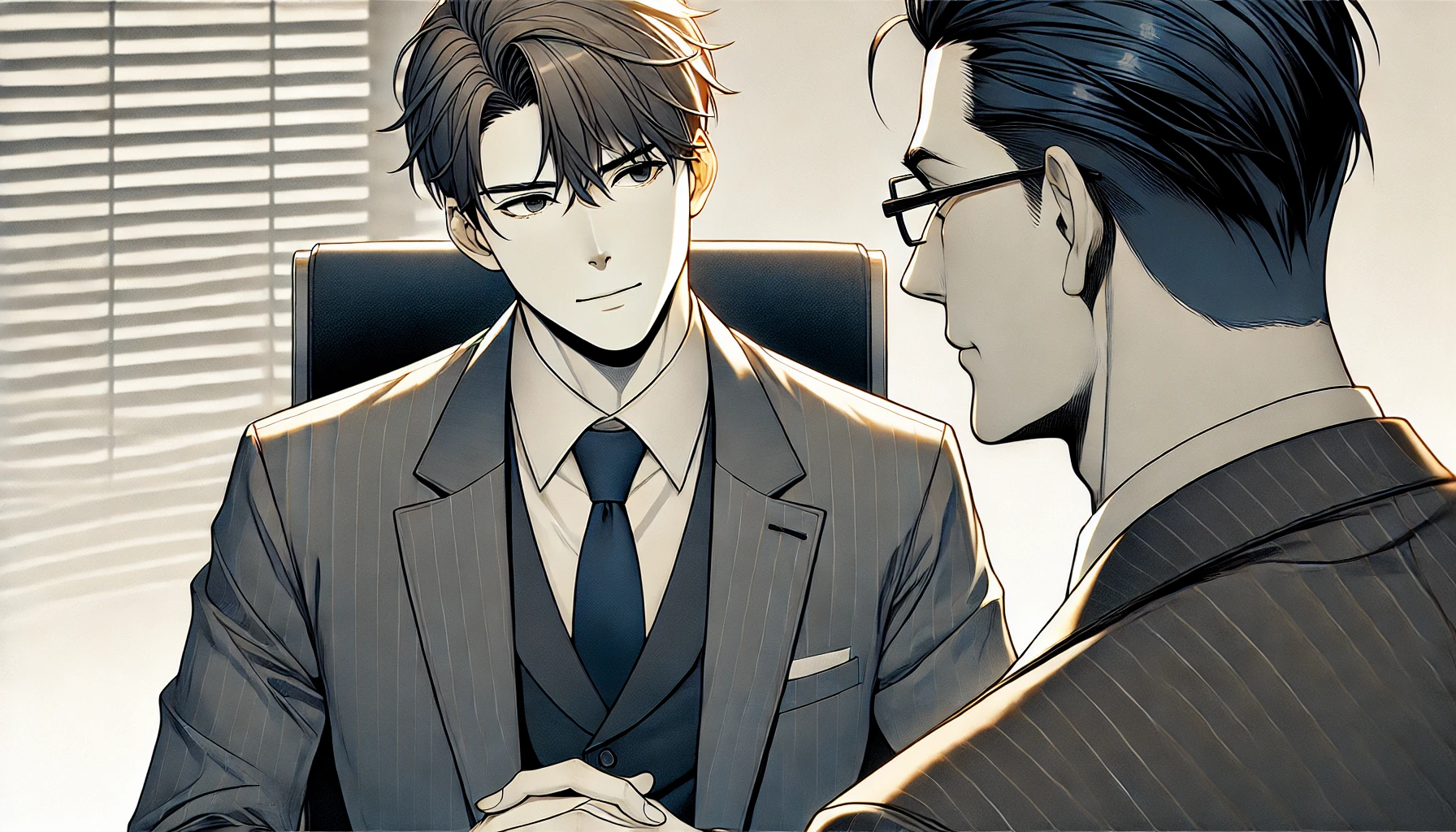
助成金の変更点、きちんと把握できていますか?
令和7年度(2025年度)からキャリアアップ助成金が大きく見直されました。特に注目すべきは、正社員化コースの助成額の減額や対象者の絞り込みなど、制度全体が「本来の目的」に回帰している点です。
これまでは高額な助成金を目当てに申請を検討する企業も多く見られましたが、今後は制度を活用する企業の「本気度」が問われる時代に入ったと言えるでしょう。
本記事では、令和7年度の制度改正を踏まえ、キャリアアップ助成金を活用したい企業が、申請前に必ず見直すべき労務管理体制について解説します。
助成金頼みの制度設計に要注意
キャリアアップ助成金は、非正規雇用者の正社員転換や処遇改善を目的とした制度であり、国が企業の人材育成を支援する重要なツールです。
令和6年度(昨年度)までは、正社員転換1名あたり最大80万円の助成金が支給されていましたが、令和7年度からは原則40万円(中小企業)に引き下げられました。重点支援対象者(3年以上継続の有期雇用労働者や母子家庭の母、派遣労働者など)に限って、40万円×2期(12か月)で最大80万円の支給となります。
このような見直しにより、助成金を「制度目的に沿って本気で活用する企業」を支援する方向へと再構築されています。つまり、単に「もらえるから申請する」という姿勢では、今後は制度に合致しづらくなっていくのです。
自由な人事運用に影響も。制度の落とし穴
実際に制度を活用する企業では、助成金要件に合わせた人事制度を設計した結果、柔軟な人事運用が難しくなるケースも見られます。
例えば、正社員転換の基準を助成金の条件(6か月以上の有期雇用契約)に合わせた場合、企業独自の評価制度やキャリアパスとの整合性が取れなくなる恐れがあります。また、助成金を活用して正社員化した人材が、必ずしも社内で即戦力になるとは限りません。
加えて、正社員転換後に会社都合退職させると助成金の受給資格を失うこともあり、人員の再配置や業務調整が難しくなるという現実的な問題も浮上しています。
このように、「助成金ありき」で設計された制度は、かえって人事政策の柔軟性を損なうリスクがあるため、導入前の慎重な判断が求められます。
助成金を活かすには“申請できる会社”に整える
キャリアアップ助成金を申請・受給するためには、法令遵守が大前提です。
具体的には以下のような体制が求められます:
- 雇用契約書や就業規則、賃金規程の整備
- 正社員転換制度や昇給ルールなどの明文化
- 社会保険・労働保険の適切な加入
- 勤怠管理や残業代支払い・年次有給休暇など、労働基準法の順守
- 過去に重大な労働法令・社会保険関連法令の違反がないこと
また、令和7年度からはキャリアアップ計画の認定手続きが簡素化され、都道府県労働局長の認定が不要になりました。とはいえ、制度の要件を満たしているかのチェックは引き続き必要であり、申請の質が問われるのは変わりません。
このように、助成金を「活かせる企業」になるためには、労務管理の基盤をしっかりと整備することが最優先事項です。制度の形式的な条件を満たすだけでなく、企業の人事方針との整合性を持たせた制度設計が成功の鍵となります。
“受けられる会社”に整える、その第一歩を
キャリアアップ助成金は、非正規雇用者のキャリア形成を真剣に支援する企業を後押しする制度です。制度の見直しにより、「申請すること」よりも「制度をどう活かすか」が問われるようになりました。
その第一歩として、自社の労務管理体制が法令遵守・文書整備・運用面で制度要件をクリアできているかを見直すことが重要です。必要であれば、社会保険労務士に相談し、申請リスクを最小限に抑えつつ、制度を最大限に活用できる設計を行うことが望まれます。
助成金は単なる「一時金」ではなく、人材育成と定着率向上につながる長期的な投資です。この機会に、制度を起点とした労務体制の強化に取り組んでみてはいかがでしょうか。
関連記事
-
最低賃金、再び大幅引上げへ?今年も注目の中賃審が始動 最低賃金、再び大幅引上げへ?今年も注目の中賃審が始動 -
No Image 労務顧問を契約すると具体的にどんなサポートを受けられる?中小企業に必須の支援内容を解説 -
「日本版DBS」制度が企業に与える影響とは?│子どもと接する業務の人材管理に注意 「日本版DBS」制度が企業に与える影響とは?│子どもと接する業務の人材管理に注意 -
熊本県の「時差出勤」大規模実証実験に企業がどう向き合うべきか 熊本県の「時差出勤」大規模実証実験に企業がどう向き合うべきか -
No Image 労務顧問契約を解約したい場合、注意すべきことは何ですか? -
【2025年最新】中途採用賃金の実態 熊本は唯一の「マイナス」伸び、今なにが起きている? 【2025年最新】中途採用賃金の実態 熊本は唯一の「マイナス」伸び、今なにが起きている?
