「10年ルール」の先にある現実──山中伸弥教授が語る研究支援者の雇い止めと、私たち中小企業が学ぶべきこと
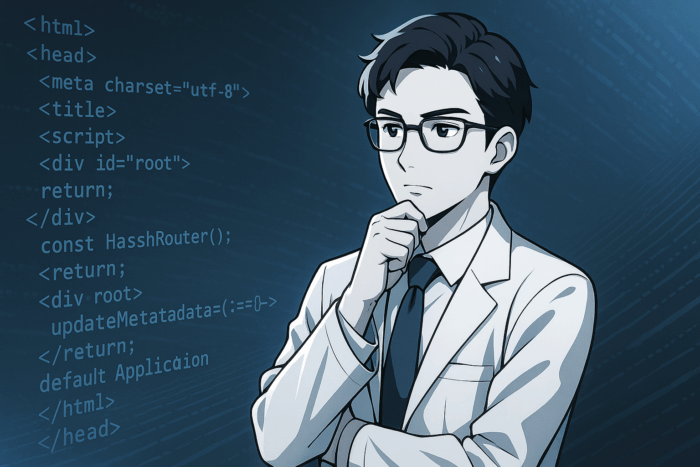
2023年、全国の大学や研究機関で起きた「雇い止め」の波。その裏にあるのは、労働契約法改正による「無期転換ルール」と、それに伴う「先延ばしの限界」でした。「10年特例」制度の特例法立案に関与した、京都大学iPS細胞研究所の山中伸弥教授は、この問題に10年前から警鐘を鳴らし、制度の間隙を埋めるため奔走してきました。
この一連の流れから、私たち中小企業が人材戦略として学ぶべきものとは何か──社会保険労務士の視点で紐解きます。
「労働者を守る法律」が、雇い止めを生む矛盾
2013年に改正された労働契約法では、「有期雇用が5年を超えると、労働者に無期転換の申込権が発生する」というルールが導入されました。
これは一見、雇用の安定を図る制度ですが、現場では思わぬ逆作用が生じます。大学や研究機関では「財源がない」「制度対応が間に合わない」との理由で、無期転換前に契約を打ち切る「雇い止め」が相次いだのです。
研究現場は、研究者だけでなく多数の「研究支援者」によって支えられています。知財管理、契約交渉、研究補助、事務手続き──彼らの雇用が不安定であれば、研究活動自体の継続性が揺らぎます。
「10年特例」は、猶予だったのか先延ばしだったのか
山中教授は、制度改正当初から「このままでは10年後に深刻な雇用問題が起きる」と訴え、特例法創設の立役者となりました。しかし10年経った今、現実は当時の懸念をなぞる形で表出しています。
教授はマラソン出場や寄付活動を通じて財源を確保し、「iPS細胞研究財団」を設立して100名規模の無期雇用体制を構築しました。これは見事な対応策ですが、制度設計や運用面での限界、そして中小規模法人ならではの持続可能性の課題にも直面しています。圧倒的な実績と知名度を持つ山中教授だからこそ成功した、という面もあり、他の大学や研究機関、あるいは企業でも同様にできるかは、疑問が残ります。
中小企業にとっての教訓:「制度」と「戦略」の間で
私たち中小企業も、労務管理において同じような問題を抱えています。
「制度に従う=従業員を守れる」とは限りません。むしろ、制度の「空白」にどう向き合うかが問われています。
たとえば、有期契約社員への対応、育成と定着のバランス、財源と雇用安定化策とのトレードオフ──これらに戦略的な判断が求められるのです。制度に準拠しつつ、独自の雇用安定策(例:正社員登用制度、評価・報酬制度の見直し、業務のマルチタスク化など)を講じる企業こそ、優秀な人材を継続的に確保できる時代です。
制度は万能ではない。企業が描く「人的資本戦略」こそ鍵
今回の山中教授のケースから見えてくるのは、「制度の先を見据える視座」と「自ら動く経営の覚悟」です。
中小企業こそ、制度依存から脱し、自社なりの雇用戦略を構築していく必要があります。働く人に選ばれる企業となるために──今こそ、雇用と人材育成の未来を真剣に考えるタイミングかもしれません。
関連情報
関連記事
-
⑨社労士事務所が提供する生成AI導入支援と継続的リスク管理サポート ⑨社労士事務所が提供する生成AI導入支援と継続的リスク管理サポート -
最低賃金1500円時代へ?―2025年度改定議論スタートと熊本県内中小企業への影響 最低賃金1500円時代へ?―2025年度改定議論スタートと熊本県内中小企業への影響 -
熊本県の飲食店で増加するカスタマーハラスメント対策|社労士が解説 熊本県の飲食店で増加するカスタマーハラスメント対策|社労士が解説 -
【熊本県企業の事例】SmartHR導入支援で実現する地方企業の人事労務DX 【熊本県企業の事例】SmartHR導入支援で実現する地方企業の人事労務DX -
2025年熊本県の最低賃金、全国最大の82円引き上げへ 中小企業経営への影響と実務対応 2025年熊本県の最低賃金、全国最大の82円引き上げへ 中小企業経営への影響と実務対応 -
No Image 「定年再雇用制度」と「継続雇用制度」の違いを解説
