「高プロ制度」導入企業、全国でわずか34社 制度設計と現場感覚のギャップが浮き彫りに
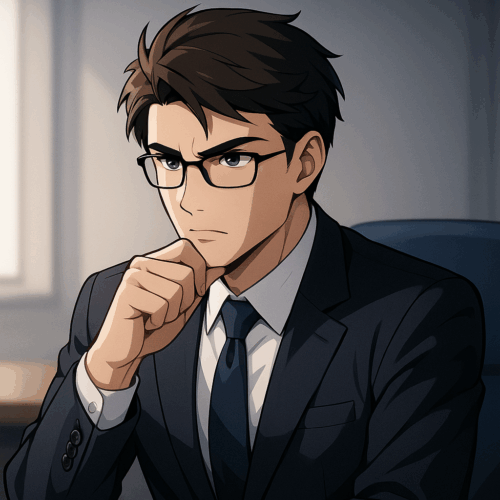
厚生労働省の最新発表によると、「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」を導入した企業数は、全国でわずか34社。制度開始から5年以上経つ今も、導入は極めて限定的です。人事制度の視点から、この数字の意味を読み解いていきます。
「高プロ制度」とは何か?
2019年から施行された「高度プロフェッショナル制度(通称:高プロ)」は、一定年収以上(現在1075万円以上)の高度専門職に対して、労働時間規制を外す制度です。高度な裁量が求められる職務において、労働時間ではなく成果で評価する仕組みとして設けられました。
導入企業は全国でわずか34社
今回の厚労省の報告(2025年3月末時点)によると、導入企業は全国で34社・36事業場。前年比で5社の増加にとどまっており、依然として「例外的な制度」であることがわかります。
内訳を見ても、
- コンサルタント:26事業場
- ファンドマネージャー:6事業場
- 新技術・サービスの研究開発:6事業場
など、専門性の高い分野に限られています。
なぜ普及しないのか?—制度と現場のギャップ
高プロは「働き方改革の柱の一つ」として打ち出された制度ですが、導入が進まない理由には以下のような要素があります。
- 対象職務が限られ、一般のホワイトカラー層には適用できない
- 労働時間規制の除外が、長時間労働の温床になるとの懸念
- 社内での制度理解や説明責任のハードルが高い
とくに地方の中小企業では「裁量労働制すら手を出していない」現実もあり、制度の理想と実態に大きなギャップがあるのです。
中小企業経営者にとっての示唆
熊本県内の中小企業において、高プロの導入は現実的とは言えません。ただし、この制度が示しているのは「成果で評価する」という潮流です。
例えば、
- 裁量を持たせた働き方への関心の高まり
- ジョブ型雇用への移行圧力
- 人事制度における「成果主義」の再検討
こうした観点は、制度導入の有無にかかわらず、人材戦略を考える上で重要です。
まとめ
高プロ制度は、ごく限られた職務・業種における「例外制度」として運用されています。中小企業にとっては直接関係ないように見えますが、「時間ではなく成果で測る」考え方そのものは、人材マネジメントの方向性として押さえておきたいポイントです。
制度の表面的な話題に流されず、自社の実情にあった制度設計・人材戦略を進めていきましょう。
関連記事
-
なぜ社会保険料は労使折半なのか? 150年の歴史が語る「資本主義の責任」 なぜ社会保険料は労使折半なのか? 150年の歴史が語る「資本主義の責任」 -
改正育児・介護休業法の対応、進んでいますか?―埼玉労働局の自主点検から見える中小企業への示唆 改正育児・介護休業法の対応、進んでいますか?―埼玉労働局の自主点検から見える中小企業への示唆 -
No Image 熊本市で労務顧問契約を結ぶときの費用相場と選び方 -
産婦への「相談窓口の情報提供」は、産後うつ病のリスクを減らし、離職・パフォーマンス低下を防ぐ 産婦への「相談窓口の情報提供」は、産後うつ病のリスクを減らし、離職・パフォーマンス低下を防ぐ -
生成AI時代のMBO―「自律型人材」を育てる目標管理と社員研修の再設計 生成AI時代のMBO―「自律型人材」を育てる目標管理と社員研修の再設計 -
熊本県で増える「人手不足倒産」を防ぐ! 地域企業向け・採用と定着の見える化支援とは? 熊本県で増える「人手不足倒産」を防ぐ! 地域企業向け・採用と定着の見える化支援とは?
