若手社員が「転勤」を理由に辞める時代に、企業が見直すべき視点とは?
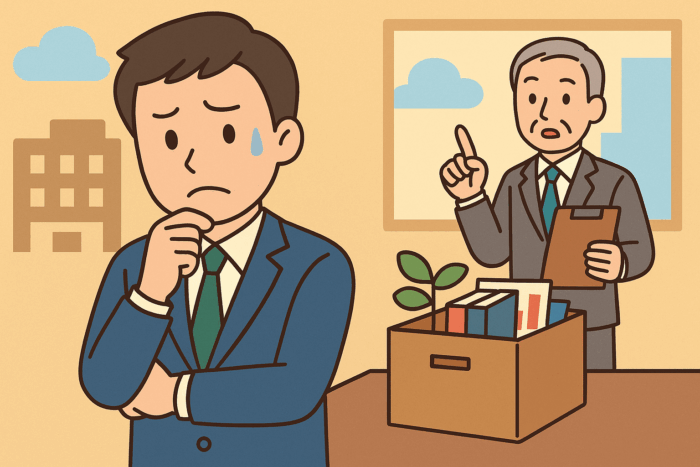
人手不足が深刻化する中で、せっかく育てた人材が「転勤」を機に辞めてしまう——。
そんな事態を未然に防ぐためには、従来の人事慣行を見直す時期にきているのかもしれません。
今回の『エン転職』のアンケート調査をもとに、中小企業が取るべき対応について考察します。
調査結果が示す“転勤”のリアル
『エン転職』が行った調査(回答者2,303名)によると、転勤経験者の44%が「転勤を機に退職を考えた」と回答。
特に20代では4人に1人が実際に退職しており、若年層ほど「転勤=辞める理由」となる傾向が顕著です。
また、今後転勤の辞令が出た場合でも、全年代で半数以上が「退職を検討する」と答えており、企業側の想定を超えた“転勤リスク”が浮き彫りになりました。
なぜ若手ほど転勤にネガティブなのか?
理由は多岐にわたりますが、主に次のような背景が見られます。
- 家族への負担、ライフスタイルの変化への懸念
- 引越しや生活基盤の再構築コスト
- 転勤によるキャリアの断絶感やモチベーション低下
また、単身赴任の割合は約7割に上り、「働き方改革」が叫ばれる中で、こうした形態が合わない世代が増えているのも事実です。
中小企業はどう対応すべきか?
熊本県内でも、製造業・サービス業を中心に、今なお「転勤」が人事ローテーションの一環として存在しています。
しかし、以下のような施策で柔軟な対応が求められます。
– 転勤を「義務」ではなく「選択肢」として扱う制度設計
→希望制、事前同意制の導入など
– 転勤に伴う支援制度の明確化・拡充
→引越し費用負担、単身赴任手当、定期帰省支援など
– 「転勤しないコース」や「地域限定職」の新設
→多様な働き方に対応し、優秀人材の定着を図る
視点:制度運用の“納得感”が鍵
社労士として現場支援を行う中で感じるのは、制度の「有無」ではなく「納得感」の有無が、従業員満足度に直結している点です。
事前説明や本人との対話の有無、家族も含めた支援体制など、「ちゃんと見てくれている」という実感が、最終的な判断に大きく影響します。
まとめ
働く人の価値観が多様化する中で、「転勤」は企業と従業員の間に潜む“見えないリスク”になりつつあります。
熊本のような地域密着型企業こそ、時代に即した柔軟な人事制度の導入が、人材確保のカギを握ります。
今後も、社労士として現場目線からの提案を続けてまいります。
関連記事
-
No Image 顧問社労士は助成金申請もサポートしてくれますか? -
賃金のデジタル払い、ついに本格運用へ?熊本県内中小企業が知っておきたいポイント 賃金のデジタル払い、ついに本格運用へ?熊本県内中小企業が知っておきたいポイント -
「荷待ち」「荷役」が減らない…熊本の運送会社が直面する“見えにくい負担”とは?【第2回】 「荷待ち」「荷役」が減らない…熊本の運送会社が直面する“見えにくい負担”とは?【第2回】 -
外国人の起業支援が本格化!熊本市のスタートアップビザ制度とは 外国人の起業支援が本格化!熊本市のスタートアップビザ制度とは -
【2025年版】同一労働同一賃金ガイドライン見直しへ──最高裁判決を反映した「7つの待遇」が焦点に 【2025年版】同一労働同一賃金ガイドライン見直しへ──最高裁判決を反映した「7つの待遇」が焦点に -
就業規則で企業文化を育てる!中小企業こそ挑みたい“第二段階”の形 就業規則で企業文化を育てる!中小企業こそ挑みたい“第二段階”の形
