「男性職員の育休取得率110.7%」の背景 山梨県の事例に学ぶ、中小企業での実践策とは
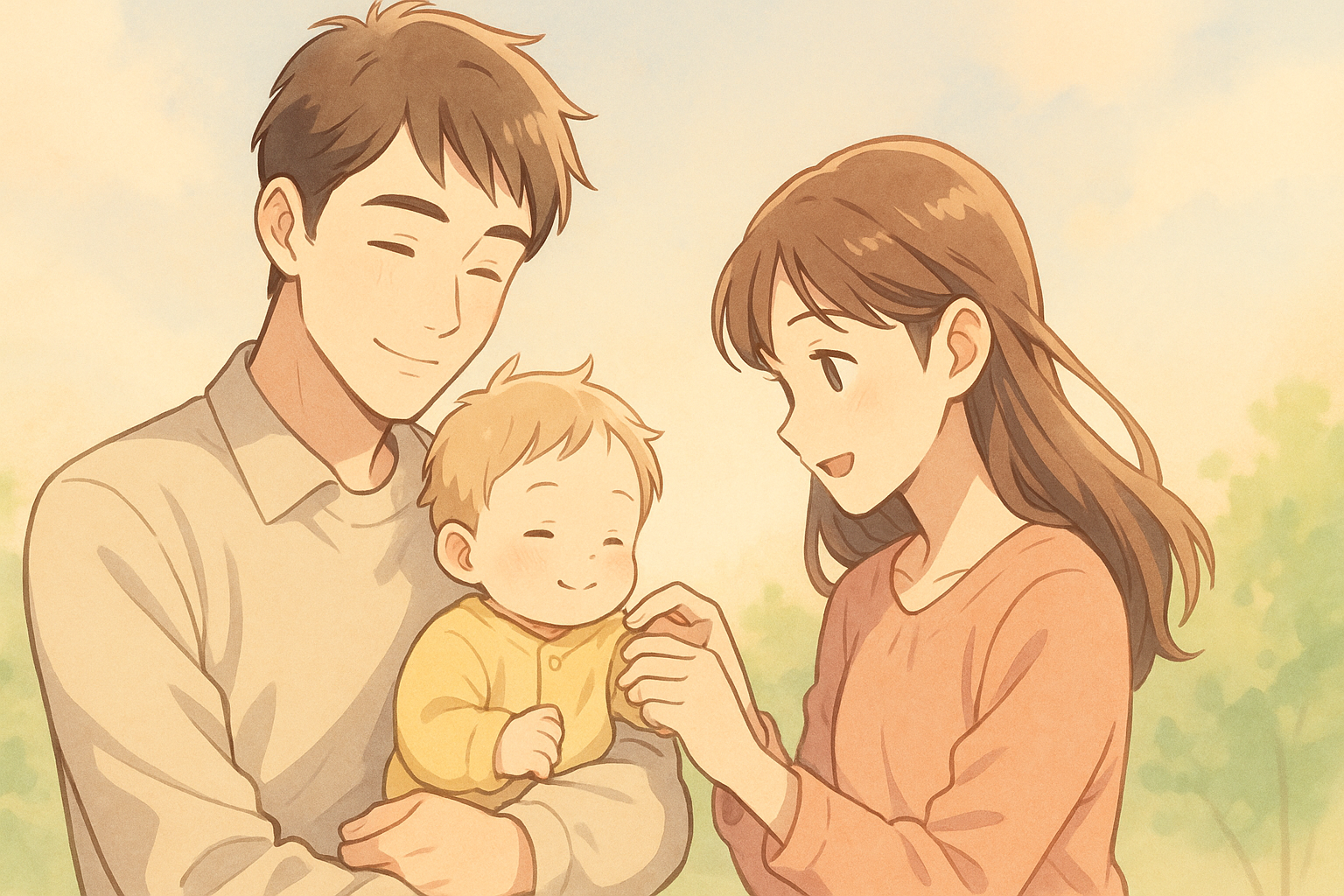
山梨県で、男性職員の育児休業取得率が「100%超え」、過去最高の110.7%に達したというニュースが話題となっています。この成果の背景には、上司による事前面談や業務分担の見直しなど、実務的かつ現実的な工夫がありました。今回は、この取り組みを通じて、中小企業においても参考になる「育休支援の仕組みづくり」について、社会保険労務士の視点から解説します。
男性の育休取得率「100%超え」の背景
山梨県では、昨年度、育児休業の取得が可能となった男性職員75人に対して、実際に取得したのは83人(110.7%)。これは、前年度に取得できず翌年度に取得したケースも含まれますが、それでも前年の64.2%から46.5ポイントの大幅上昇です。
注目すべきは、その成果の裏にある具体策です。
- 上司が事前に面談し、子育て支援計画を策定
- 育休取得時の業務分担の見直し
このような職場での実務的な支援が、取得率向上に大きく貢献しました。
熊本県内中小企業にとっての示唆
中小企業にとって、「人がいない」「業務が回らない」といった事情から、男性の育休取得はまだハードルが高いと感じられているかもしれません。ですが、今回の山梨県の事例は「制度」だけでなく、「現場の工夫」次第で文化が変わることを示しています。
例えば、
- 子どもが生まれる予定の社員と上司の1on1ミーティング
- 育休取得前後の業務フローの棚卸しと分担の見直し
- 育休中の連絡ルールや復帰支援のルール化
など、低コストでも実現可能な施策があります。
社会全体へ波及させるために
県は「子育てしやすい環境を社会全体へ波及させたい」と述べています。これは決して官公庁だけの話ではありません。むしろ、地域密着で社員との距離が近い中小企業こそ、柔軟な運用が可能です。
従業員のライフイベントに寄り添える企業こそが、これからの採用・定着戦略の中心になります。山梨県の成果を一つのヒントに、ぜひ自社でも育児休業制度の「実効性」を高める取り組みを進めてみてください。
荻生 清高(社会保険労務士 荻生労務研究所 代表)
関連記事
-
熊本大学×日本商工会議所青年部の人材育成協定に注目:地域経営者にとっての意味とは? 熊本大学×日本商工会議所青年部の人材育成協定に注目:地域経営者にとっての意味とは? -
熊本県内企業の景気見通しに「不透明感」— 2026年、中小企業がまず整えるべき“人と生産性”の備え 熊本県内企業の景気見通しに「不透明感」— 2026年、中小企業がまず整えるべき“人と生産性”の備え -
中小企業の人材育成、今こそ「伴走型支援」の活用を 厚労省報告書が示す未来戦略 中小企業の人材育成、今こそ「伴走型支援」の活用を 厚労省報告書が示す未来戦略 -
No Image 熊本市で労務顧問を探す前に確認すべきサポート内容一覧 -
「デジタル化」で終わらせないために 長野の中小企業が挑んだ本当のDXとは 「デジタル化」で終わらせないために 長野の中小企業が挑んだ本当のDXとは -
36協定の無効が命取りに? 外国人実習生の残業で送検、他人事ではない36協定のリスク 36協定の無効が命取りに? 外国人実習生の残業で送検、他人事ではない36協定のリスク
