育休は『福利厚生』から『経営課題』へ──熊本の中小企業が今こそ考えるべき視点とは
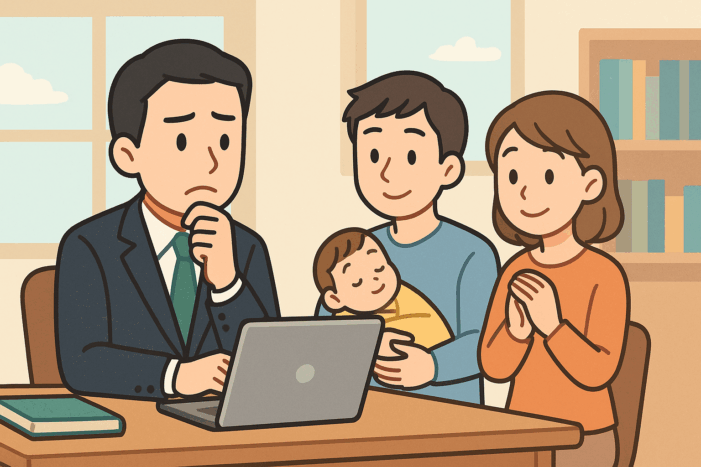
育児休業の取得率が上昇する中で、実は「育休の質」こそが企業に問われる時代が始まっています。
男性の育休取得に関する不利益扱いの相談が増える一方で、先進的な企業では社内文化や制度の見直しが進んでいます。
本記事では、育休に関する最新の動向と、熊本県内の中小企業が直面する課題、そして具体的な対策について考えます。
育休取得率から『育休の質』へ
厚生労働省の調査では、男性の育休取得率は年々増加しています。
しかしその一方で、希望する期間を取得できない、あるいは取得後に職場で不利益な扱いを受けるといった声が増えています。
単なる「取得率の向上」では不十分で、育休中・復帰後のサポート体制、組織内での理解度、そしてキャリアへの影響のなさといった『質』が求められるようになっています。
「取らせたが、評価を下げた」では、真の両立支援とは言えません。
育休をめぐる不利益取り扱いの現状
実際、全国の労働局に寄せられた「育休を理由に不利益な扱いを受けた」という相談は2024年度には5,317件。3年連続で増加しています。
なかには、男性社員が長期育休を取得した後に「男のくせに育休を取った」と非難され、降格されたという事例もあります。
育児・介護休業法では、育休を理由とした不利益な取り扱いは禁止されていますが、現場ではまだ十分に認識されていないケースが多いのが実情です。
先進企業の取り組みに学ぶ
パーソルキャリアでは、男性社員の9割が育休を取得し、その平均取得日数は約69日。
さらに、上司が抜き打ちで帰宅させられる研修を実施し、育児に関する急な対応を体感させることで管理職の理解を促進しています。
また、三井住友銀行では、育休を取得した社員の同僚に報奨金5万円を支給する制度を開始し、「送り出す側」の支援も始めています。
これらの事例は、制度設計だけでなく、職場文化やマネジメントのあり方そのものを見直している点が特徴です。
中小企業が今からできる対策とは
「大企業だからできる話」と片付けてしまう前に、中小企業としてもできることはあります。
たとえば、育休取得後の復帰支援面談、業務の属人化を防ぐ仕組み、急な育児対応時のチームフォロー体制の整備など、小さな工夫の積み重ねが「育休の質」を支えます。
まずは、経営者自身が「育休はキャリアに不利益をもたらさない」というメッセージを発信すること。これが、社内の風土を変える第一歩となります。
まとめ
育休取得の時代は、量から質へと移行しています。
経営者として重要なのは、制度を用意すること以上に、利用しやすい風土をどう作るかです。
育児期のサポートは、社員の定着や生産性向上、さらには採用力の強化にもつながります。
熊本の中小企業でも、できるところから一歩ずつ始めてみませんか?
関連記事
-
No Image 熊本市で労務顧問を探す前に確認すべきサポート内容一覧 -
建設業の働き方改革に学ぶ|時間外労働の上限規制にどう対応するか 建設業の働き方改革に学ぶ|時間外労働の上限規制にどう対応するか -
ペーパーレス&ミスゼロ! 創業初期にクラウド型労務管理を導入するメリット ペーパーレス&ミスゼロ! 創業初期にクラウド型労務管理を導入するメリット -
2026年10月「カスハラ対策義務化」へ──熊本の中小企業が今から整えるべき3つのポイント 2026年10月「カスハラ対策義務化」へ──熊本の中小企業が今から整えるべき3つのポイント -
No Image 熊本市の中小企業で「36協定」の未提出が労基署の是正勧告に発展した事例 -
職場の飲み会、実施率が大幅減少。変わる職場の「つながり」の形とは? 職場の飲み会、実施率が大幅減少。変わる職場の「つながり」の形とは?
