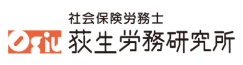無断欠勤を続けた社員は、処分を経て普通解雇すべきか? 自然退職を適用すべきか?/リハビリ出勤の復職可否判断【ツキネコほか事件 東京地裁令和3年10月27日判決 ほか】

社会保険労務士の、荻生清高です。
無断欠勤を続けて、出勤しない従業員。
そして、傷病でリハビリ出勤させた従業員の、復職可否の判断。
いずれも企業にとって、頭の痛い問題です。
今回はこれらに対し、参考となる裁判例を紹介します。
ツキネコほか事件の概要
この事件は、会社が原告労働者Xとの面談やリハビリ出勤を通し、Xに適性のある職種はないと判断し、退職勧奨を行ったものです。
また、Xはこれと併せて行われた、原職と異なる職場への復職命令にも応じず、無断欠勤を続けました。
会社はこれに対し、まず減給処分を行いましたが、それでも無断欠勤を続けたため、普通解雇したものです。
Xは退職勧奨が違法であること、そして原職への復職を訴え、併せてその間の賃金支払を求めて裁判を起こしました。
裁判所はXの請求をすべて退け、会社勝訴の判決を出しました。
なぜ会社の退職勧奨、そして減給処分と普通解雇が認められたのか?
ここからは、なぜ会社の対応が全面的に認められたのかを、読み解いていきます。
退職勧奨について
まず前提として、会社は退職勧奨を行うことは、自由にできます。
適切に行えば、退職勧奨が不法行為になることはありません。
ただし、以下のように判断されると、退職勧奨が無効とされる場合があります。
- 労働者の自由な意思・判断を失わせるように行われた場合(労働者が断っているのに執拗に退職を迫り続けたなど)
- 労働者の名誉感情を侵害した場合(多くの人の目の前で、侮蔑的な表現で行ったなど)
このような行為は、退職勧奨でなく退職強要と判断されますので、気をつけなければなりません。
さて裁判所は、以下の事実を認め、退職勧奨が有効としました。
- 退職勧奨の頻度、回数はやや多いものの(7カ月余りの間に、面談を21回行っていた。退職勧奨は16回から18回目にかけて実施)、退職勧奨で対象労働者の自由な意思形成を阻害してはいなかったこと(原告の復職には応じない・原告を辞めさせるなどと発言してはいなかった)
- 会社はその間も引き続き、復職命令を発していたこと
- 会社はXとの面談、リハビリを行った結果、労働者に適性のある職種はないと判断し、その結果を原告に伝えたこと
このほか、Xがこの間、退職勧奨に対して明示的に拒絶していなかったことも、考慮しています。
裁判所はこの点を踏まえ、退職勧奨を有効と認めました。
復職命令の有効性
まず、会社が行った復職命令の判断は、Xの体調に配慮する対応を行っていたことなどから、有効としています。
そして、元の職場である開発業務に復職させず、別の職場への復職命令を下したことも認めました。
- 元の職場の上司とのトラブルを発端に、精神疾患を発症したこと
- Xの主治医も、外部と接触する業務と開発業務は避けた方がいいと指摘したこと
また、リハビリ期間は、会社に賃金支払義務が生じるような労働ではないことを、明確にして対応していました。
- リハビリ期間中は、休職を前提に傷病手当金を受給させていたこと
- 面談の際、リハビリを経て復職した時点で給与が発生することを、話し合っていたこと
減給処分・普通解雇の有効性
Xは復職命令を発令した後も、これに応じることなく無断欠勤を続けました。
会社はその後何度か出勤を求めるも、無断欠勤を続けたため、1ヶ月の減給処分を経て普通解雇しました。
Xは解雇無効を訴えましたが、裁判所はXの請求を退け、解雇成立を認めました。
減給処分および普通解雇の有効性についての、裁判所の判断のポイントは、以下の通りです。
- 会社はその後4ヶ月間にわたり、4回にわたり出勤を求めたり、出勤できない場合は面談をしたいので都合がつく日を連絡するよう、粘り強く呼びかけ続けたこと
- それでも無回答のまま無断欠勤を続けたXに対し、就業規則に基づき「3ヶ月以上の無断欠勤が続いている」とし、1ヶ月の減給処分を行ったこと
- この処分後も会社は引き続き、出勤を求め続けたこと
- それでもXからの回答がなかったため、就業規則の定めに基づき、Xを普通解雇したこと
会社の粘り強い取り組みが、裁判所に評価されたと思われます。
無断欠勤する労働者を、懲戒を経ての普通解雇と「自然退職ルール」と、どちらがいいのか?
無断欠勤を続ける労働者への対策でよくあるのが、就業規則の退職理由に「○日以上行方不明となり連絡が取れず、解雇手続を取らない場合」という規定を設けることです。
いわゆる自然退職ルールですが、この規定に従えば、本件のように懲戒処分や普通解雇を経ることなく、素早く手軽に対応できます。
本件の対応と、この「自然退職ルール」での対応と、どちらが適切かが問題となります。
O.S.I事件(東京地裁令和2年2月4日判決)
自然退職ルールによる退職が、争点になった裁判例に、O.S.I事件があります。
この裁判例では、会社は次のような就業規則を定めていました。
「従業員の行方が不明になり、14日以上連絡が取れないときで、解雇手続を取らない場合には退職とし、14日を経過した日を退職とする」
会社はこの規定を適用し、従業員を自然退職としました。
O.S.I事件に対する、裁判所の判断
会社は従業員に電話をかけるも、1回しか応答せず、また自宅を訪ねても応対しなかったとしています。
しかし、それまで原告労働者がFaxや電子メールを送り、会社とやり取りしていた事実がありました。
裁判所はこの事実を踏まえ、電話や自宅訪問で連絡を取ることができなくても、Faxや電子メールを利用して通知や意思表示を行うことができた状況だったのに行わなかったと、厳格に解釈しました。そして「行方が不明になり、14日以上連絡が取れないとき」にあたる状況だったと、認めませんでした。
会社には酷な結論でしたが、裁判所は自然退職規定が有効であることは、前提にしていると思われます。
結局、会社はどうすればいいのか?
現時点で、就業規則の自然退職規定の効力そのものを否定した裁判例を、見つけることはできていません。
一方でO.S.I事件は、本人の言動・および会社の対応に、若干イレギュラーな面がありますので、この判決を踏まえての対応を、現時点では控えています。
筆者は現時点では、自然退職ルールの迅速さ・簡便さには、一定の意義があると考えています。
今のところは、それぞれの会社の状況、および要望をもとに、どのルールが適切かを、個別の会社ごとに協議して対応しています。
10人未満でも就業規則を作っていない会社、就業規則が古い会社は要注意
無断欠勤による退職、あるいは減給・普通解雇は、就業規則には通常設けられます。
ただ、筆者が見る限り、就業規則を定めていない会社は、よく見受けられます。
就業規則はそもそもいらない、10人未満の会社だからいらない、プロに任せるとお金がかかるから自分で何とかすればいい。
そう解釈して、就業規則を作っていない会社は多いです。
あるいは、何年も前に作った就業規則が、誰の目にも触れずにホコリをかぶっている。
これも、意外とよくある例です。
自然退職ルールおよび減給、そして戒告や懲戒解雇などの制裁、そして普通解雇は、就業規則に定めがなければできません(労働基準法、労働契約法による)。
これは、10人未満の会社であっても同じです。
就業規則を作っていない、あるいは作っていても誰も見ていない。
この状態では、就業規則は無効となり、減給その他懲戒も普通解雇もできません。
早急な対応が必要ですので、社労士にご相談ください。
関連記事
-
寄稿「男性育休で人手不足を解決する方法」が、「KUMAMOTO地方経済情報」10月号に掲載されます。 寄稿「男性育休で人手不足を解決する方法」が、「KUMAMOTO地方経済情報」10月号に掲載されます。 -
著書「4人以下の小さな会社・ひとり社長の労務管理がこの1冊でわかる本」が、熊本日日新聞で紹介されました。 著書「4人以下の小さな会社・ひとり社長の労務管理がこの1冊でわかる本」が、熊本日日新聞で紹介されました。 -
No Image -
裁判例評釈【アムール他事件 フリーランスへのセクハラ・パワハラ防止および安全配慮義務】 裁判例評釈【アムール他事件 フリーランスへのセクハラ・パワハラ防止および安全配慮義務】 -
103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁 ってナニ? &支援措置 ~年収の壁・支援強化パッケージ~ 103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁 ってナニ? &支援措置 ~年収の壁・支援強化パッケージ~ -
No Image 会社都合退職にしてほしいという要望があった。応じてもいいか?