速報解説:男性の育休取得率40.5%|中小企業が今すぐ取り組むべき4つのステップ
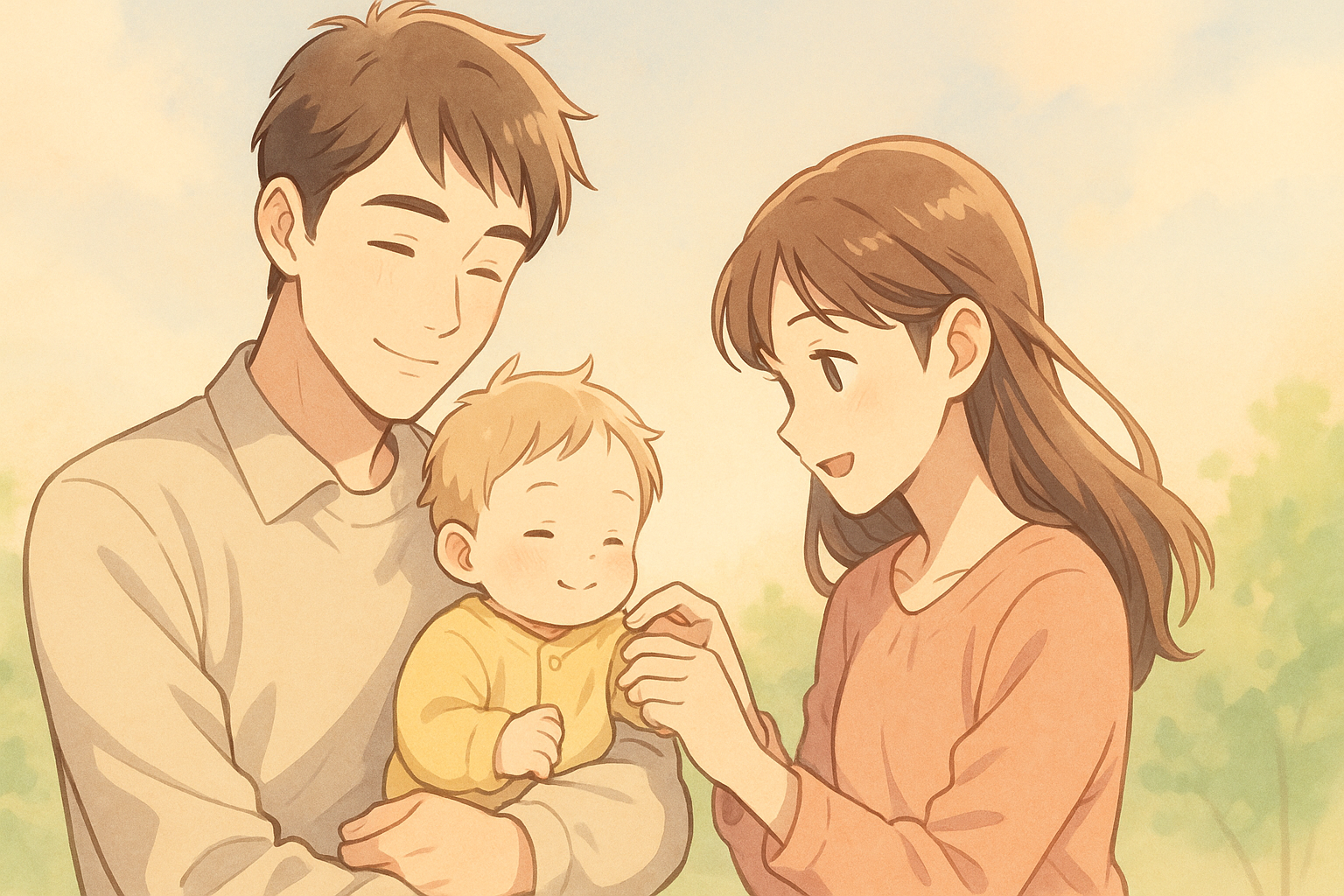
厚生労働省が2025年7月30日に公表した令和6年度「雇用均等基本調査」によれば、男性の育児休業取得率が40.5%と初めて4割を突破しました。前年から10.4ポイントの大幅増で、政府目標(2025年に50%)達成が現実味を帯びています。熊本県内の中小企業にとっても、人材確保とエンゲージメント向上の好機です。社会保険労務士の視点で要点と具体策を整理します。
育休取得率増加の背景と今回のポイント
- 男性育休取得率40.5%(前年比+10.4pt)で過去最高。
- 取得者の大半が「産後パパ育休」(出生時育児休業)を活用。
- 女性の取得率は86.6%と高水準を維持。
- 政府目標は2025年:男性50%/2030年:男性85%。
取得率急上昇を後押しした3要因
- 法改正(2022年10月〜)
出生時育児休業の創設により、子の出生後8週以内に最大4週を柔軟に分割取得可能となる。 - 企業への取得意向確認の義務化
本人または配偶者の妊娠・出産等の予定を申し出た従業員に対し、企業が育休等取得意向を確認する義務が明文化。 - 社会的認知度の向上
SNS・メディア露出で「産後パパ育休」が広まり、取得しやすい雰囲気が醸成。
中小企業が直面するリアルな課題
- 代替要員確保の難しさ:少人数現場で1名欠けるだけで業務停滞リスク。不公平感から「子持ち様」など社内不和を招くリスクも。
- 制度設計の複雑さ:就業規則や労使協定の整備不足で運用が滞る。
- コスト意識のギャップ:助成金・給付金を知らず「負担増」と誤解。
- 職場文化:トップが後押ししなければ「取りにくい雰囲気」が残存。
熊本県内で活用できる支援策
- 熊本市「子育て支援優良企業」認定:2025年4月時点で75社が認定済み。採用広報で「子育てにやさしい職場」をPR可能。
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース):要件を満たせば最大60万円を受給。
- 熊本労働局の無料個別相談:就業規則改訂・助成金申請をサポート。
すぐに始められる4つのステップ
- 方針を明文化し全社員へ周知
社長が「男性育休を推進する」と明言し、イントラ・朝礼で繰り返し発信。 - 就業規則・育休規程のアップデート
育児休業の分割取得、取得など新制度に即した条文へ改訂。 - 代替要員を確保する仕組みづくり
業務フローを細分化し、パート・派遣・業務委託でカバーできる部分を洗い出す。 - 助成金・認定制度の活用
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)申請と熊本市「子育て支援優良企業」認定を同時に進行。
6. まとめと次の一手
男性育休はコストではなく、優秀な人材を惹きつけ定着させる投資です。取得率が40%を超えた今、対応の遅れは採用競争力を大きく損ねます。まずは社内ルール整備と助成金・地域認定の活用で、最小限のコストで取り組みを加速しましょう。
ポイント:制度改正から3年目に入り、先行企業との差が一気に広がるタイミングです。社労士と連携し、「取得しやすい職場づくり」を次の経営戦略に組み込みましょう。
(執筆:荻生 清高/社会保険労務士 荻生労務研究所)
ご質問・ご相談はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
関連記事
-
熊本大学医局パワハラ問題にみる「人事の支配構造」 中小企業が学ぶべき組織運営の教訓 熊本大学医局パワハラ問題にみる「人事の支配構造」 中小企業が学ぶべき組織運営の教訓 -
「男性育休」導入の背景:出産直後に男性が育児に関わるか否かが、生涯の夫婦円満に影響する 「男性育休」導入の背景:出産直後に男性が育児に関わるか否かが、生涯の夫婦円満に影響する -
熊本の運送業者の皆様へ 労働時間上限規制の重要ポイント 熊本の運送業者の皆様へ 労働時間上限規制の重要ポイント -
日本版DBSガイドライン素案公表:子どもに関わる事業者が今から準備すべきこと 日本版DBSガイドライン素案公表:子どもに関わる事業者が今から準備すべきこと -
歩合給の効力が否定された裁判例【サカイ引越センター事件 東京地裁立川支部令和5年8月9日判決】 歩合給の効力が否定された裁判例【サカイ引越センター事件 東京地裁立川支部令和5年8月9日判決】 -
鹿児島市役所の働き方改革に学ぶ:熊本の中小企業が検討すべきポイントとは 鹿児島市役所の働き方改革に学ぶ:熊本の中小企業が検討すべきポイントとは
